\スグに読める/
\30秒で申込完了/
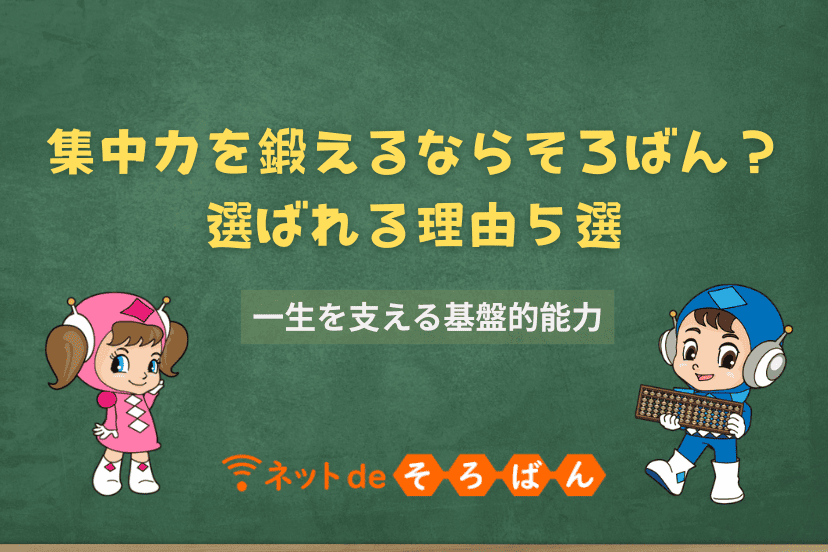


「なかなか集中力が続かなくて…」
そんな悩みを抱える保護者は少なくありません。スマホやゲームなど刺激があふれる現代では、子どもが一つのことにじっくり取り組む力を育てるのがますます難しくなっています。
ところが近年、意外にも“昔ながら”とされてきた「そろばん」が、子どもの集中力を高める習い事として再び注目を集めています。
右脳と左脳をバランスよく使いながら計算に没頭するそろばん学習は、科学的にも脳の持続的な注意力や情報処理能力を鍛える効果があることが報告されています。
本記事では、なぜ今そろばんが集中力アップの習い事として選ばれているのか、最新研究結果とともにその理由を5つご紹介します。

子どもたちの集中力が年々低下していることが、複数の調査で明らかになっています。
文部科学省が全国の小中学生を対象に実施した「全国学力・学習状況調査」では、授業中に「いつも集中している」と答えた小学生は2012年度の54.4%から2022年度には44.5%へと約10ポイントも減少し、中学生も39.5%から31.6%へと同様の傾向を示しました(文部科学省, 2022)。
さらに東京都教育委員会が行った調査でも、コロナ禍以降に「授業に集中できない」「気が散りやすい」と感じる児童生徒が増えていることが報告されています。
背景には、スマートフォンやタブレットなどデジタル機器の長時間使用や生活リズムの乱れがあり、子どもたちが一つのことに没頭し続ける力を保つことが難しくなっているのです。

スマートフォンやタブレット、動画コンテンツなど、子どもが触れるデジタル機器の利用時間が急増しています。都内を中心に授業で使われる事も増えてきています。
総務省の「令和5年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、小学生の平日1日あたりのスマートフォン利用時間は平均約77分に達しており、5年前に比べて約2倍となっています。
日本大学文理学部の研究では、1日2時間以上タブレットを使用する児童は、持続的注意力のスコアが有意に低いことも示されています。
次々と刺激が切り替わるコンテンツに慣れてしまうことで、脳が一つのことに集中し続ける力を発揮しづらくなっているのです。

集中力の持続には、十分な睡眠や規則正しい生活リズムが欠かせません。
しかし近年、就寝時間の遅れや睡眠時間の不足が子どもたちの間で問題となっています。国立成育医療研究センターが行った調査では、小学生の約30%が平日6時間未満の睡眠しか取れていないと報告されました。
慢性的な睡眠不足は脳の前頭葉の働きを低下させ、注意力・判断力・記憶力を著しく損なうことが複数の脳科学研究でも示されています。生活習慣の乱れが、学習中に集中できない一因となっているのです。
特に習い事を掛け持ちしている子どもほど、この傾向は顕著です。(睡眠不足の子どもが半数以上、塾やスマホ利用で…昼夜逆転し不登校になる生徒も)

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、長期休校やオンライン授業が導入されたことで、子どもたちの学習環境は大きく変わりました。
東京都教育委員会の調査では、コロナ禍以降に「授業に集中できない」「気が散りやすい」と感じる児童生徒が増えたと報告されています。
学校や塾での対面学習やグループ活動が減少し、周囲と切磋琢磨する刺激が少なくなったことも、集中力の低下を招いたと考えられています。
東京大学大学院医学系研究科が行った調査(2021年)では、在宅勤務が長期化したビジネスパーソン約3,000人を対象に心理的影響を調べたところ、約42%が「集中力が低下した」と回答しています。
また、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症とメンタルヘルスに関する調査」(2022年)でも、テレワークが続いた人ほど注意力や作業効率の低下、作業中の気の散りやすさを感じやすい傾向が報告されました。理由としましては、子どもと同様に対面での刺激や社会的交流が減ったことが挙げられます。
オックスフォード大学の研究(2021)では、人は他者と関わることで前頭前野が活性化し、認知機能が維持されると示されました。対面コミュニケーションの減少により、脳が「集中モード」に入りにくい状態になっていたと考えられます。
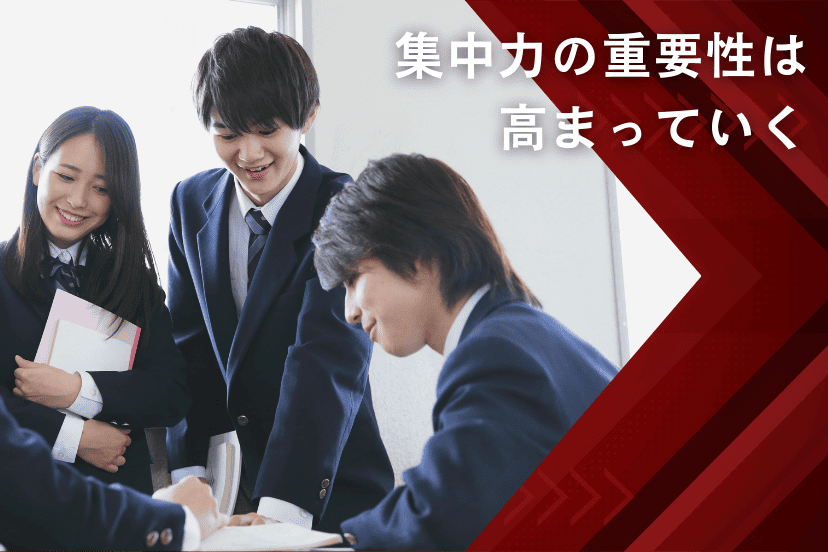
学習が進むにつれ、そして大人になるにつれて、集中力の重要性は格段に高まっていきます。
小学校低学年までは短時間で終わる簡単な宿題が中心で、集中が途切れても再開しやすい環境にあります。しかし学年が上がるにつれて、複数の情報を整理しながら筋道を立てて考える必要があるため、長時間にわたって注意を維持する力が不可欠になります。
特に中学・高校以降は、入試や定期テストといった「時間制限のある集中作業」が増えるため、集中力の差が学力差に直結しやすくなります。
さらに大学や社会に出ると、集中力は単なる学力以上に「仕事力」として求められます。限られた時間で膨大な情報を処理し、判断や意思決定を正確に行うには、高い集中力が欠かせません。
実際、経済協力開発機構(OECD)のスキル・アウトルック報告書では、今後の社会で特に重要になる能力のひとつとして「持続的集中力(sustained attention)」が明記されています。
つまり集中力は、子ども時代の学力向上だけでなく、大人になってからの生産性や創造性、キャリア形成にまで影響する「一生を支える基盤的能力」と言えるのです。
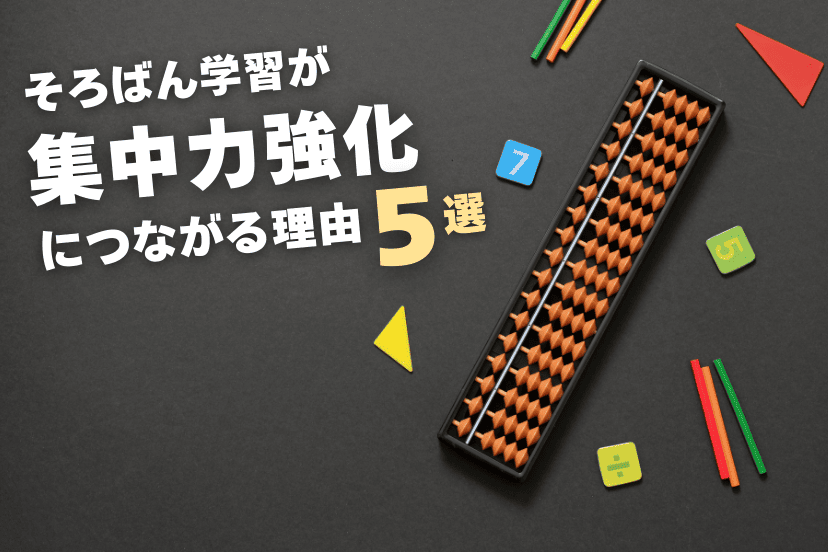
集中力を高めたい子どもに、なぜ今「そろばん」が注目されているのでしょうか。
かつては暗算力や計算スピードを鍛える習い事とされていました。しかし、最近の脳科学研究では、集中力そのものを育てる効果があることが次々と明らかになっています。
実際、そろばん経験者は授業中に注意を持続できる時間が長いという調査結果も報告されています。では、なぜそろばんが集中力を高めると言われるのでしょうか。その根拠となる5つの理由を科学的視点から詳しく解説していきます。
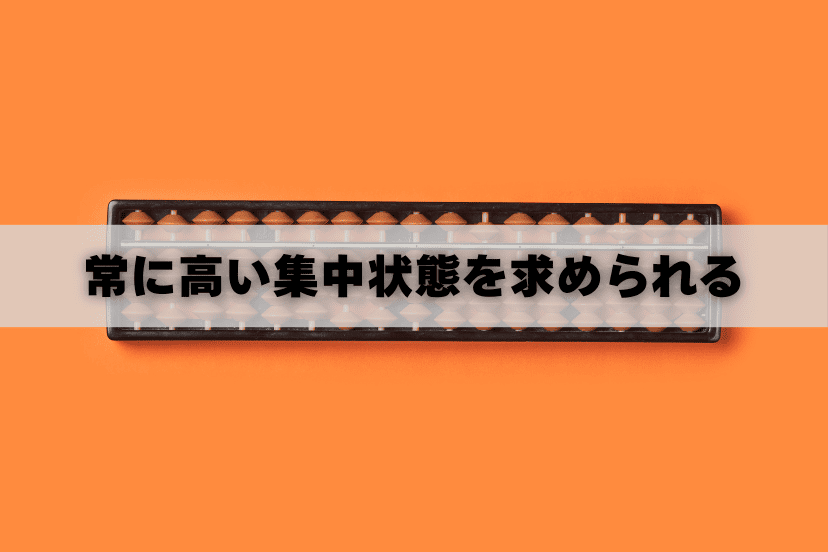
そろばん学習では、制限時間内に多くの計算問題を正確に解かなければなりません。
一問でも気を抜いてしまうとすぐに計算ミスにつながるため、常に高い集中状態を維持する必要があります。
このように一瞬の油断も許されない緊張感の中で繰り返し練習することで、自然と集中力が鍛えられていきます。特に、そろばんでは「時間制限」がある練習が多く行われるため、短時間で深く集中する力(選択的注意)と、それを持続する力(持続的注意)の両方が育ちます。
実際、日本珠算連盟が実施した調査では、そろばん経験者の小学生は非経験者に比べて授業中の集中持続時間が平均で約1.5倍長いことが報告されています。
こうした結果は、そろばんが単なる計算練習ではなく、「集中する力そのものを鍛えるトレーニング」であることを示しています。
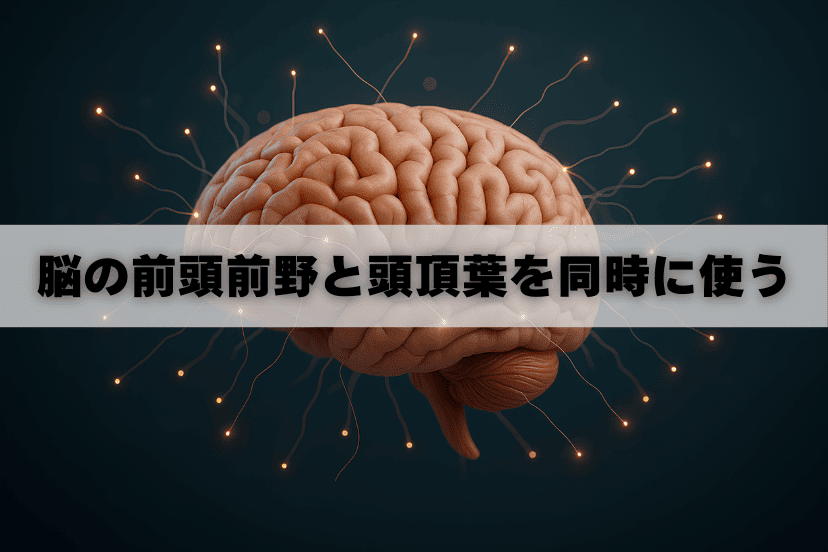
そろばんの計算は、単に数字を足し引きするだけでなく、目で見た珠の位置を空間的に把握しながら指先で素早く操作し、その結果を次の計算につなげるという複雑な処理を伴います。
この過程では、注意力や判断力、ワーキングメモリを担う前頭前野と、視覚的・空間的処理を担う頭頂葉を同時に使うことが知られています。
京都大学の研究でも、そろばん経験者は非経験者に比べて前頭前野と頭頂葉の機能的結合が強化されていることが示されており、これが集中力や思考の持続性を高める要因になっていると考えられています。
脳科学の観点から見ると、そろばんは「集中力を発揮するための脳のネットワーク」を効率的に鍛える学習とも言えるのです。
脳内ネットワークの発達は小学生期にピークを迎えるため、この時期にそろばんで前頭前野と頭頂葉を同時に刺激する学習は、将来にわたって集中力の土台を築くうえでも非常に大切です。
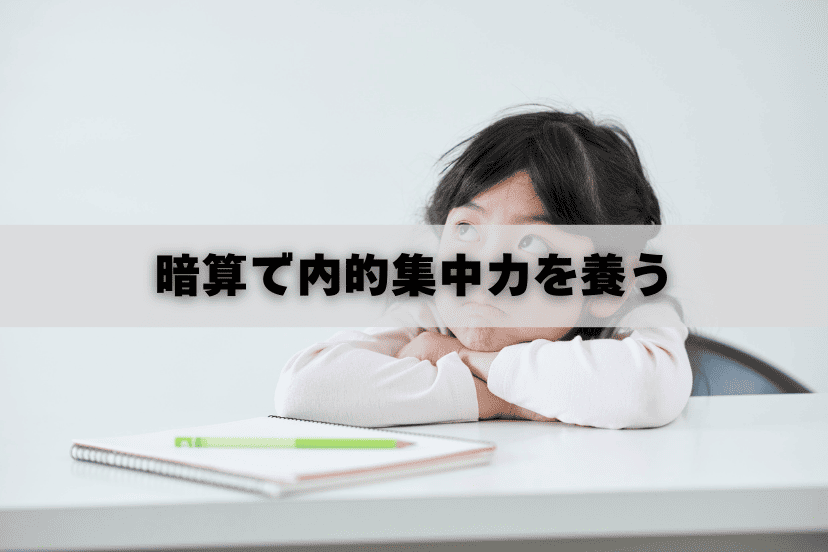
そろばんを一定期間学習すると、子どもたちは実際のそろばんを使わずに頭の中で珠を動かして計算する「そろばん式暗算(イメージそろばん)」ができるようになります。
これは周囲の刺激を遮断し、自分の頭の中だけでイメージを操作する高度な認知活動です。外部からの視覚や聴覚刺激を無視して自分の内側のイメージに集中することは、心理学的には「内的注意制御」と呼ばれ、持続的集中力を鍛えるうえで極めて効果的だとされています。
実際、東京大学と日本珠算連盟が共同で行った研究では、そろばん式暗算が得意な児童は注意集中テストで有意に高いスコアを示し、「周囲の音や動きに気を取られにくい」傾向があると報告されています。
このように、そろばんは単に計算力を高めるだけでなく、外的刺激に左右されずに集中する「内的集中力」を育てるという、他の習い事には少ない特性を持っているのです。
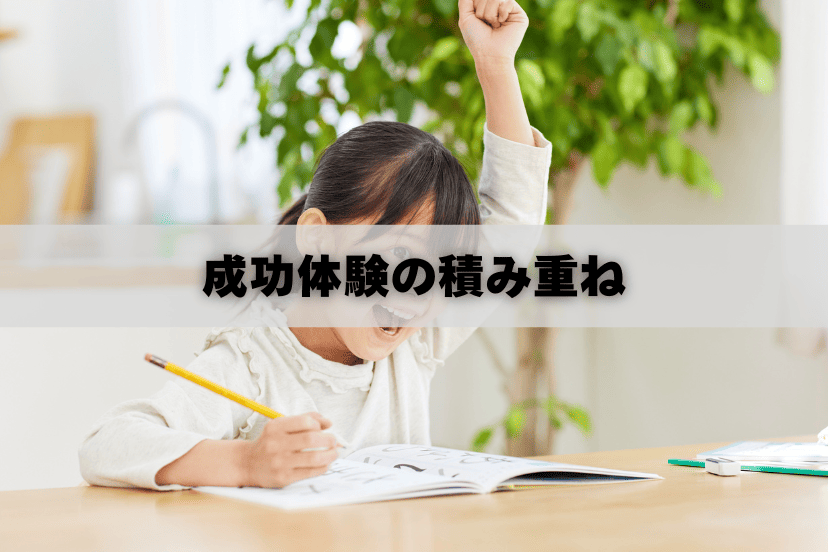
そろばんでは、級や段の検定試験、大会、日々の練習記録など、明確な目標を設定して取り組む機会が多くあります。
子どもたちは「今日は10問連続で正解できた」「前より速くできた」といった小さな成功体験を積み重ねることで、集中することへの心理的ハードルを下げていきます。
この「集中=大変」ではなく「集中=楽しい・達成感がある」という感覚が芽生えると、自然と集中時間も長くなっていきます。
教育心理学の研究では、達成感や有能感が集中力や自己制御力を高めることが知られており、そろばんはまさにその成功体験の繰り返しを提供する習い事です。
最初は数分しか集中できなかった子どもでも、毎日少しずつ成功を積み上げることで、次第に長時間集中する耐性が育まれていきます。こうして身につけた集中力は、他教科の学習や将来の仕事でも大きな武器になります。
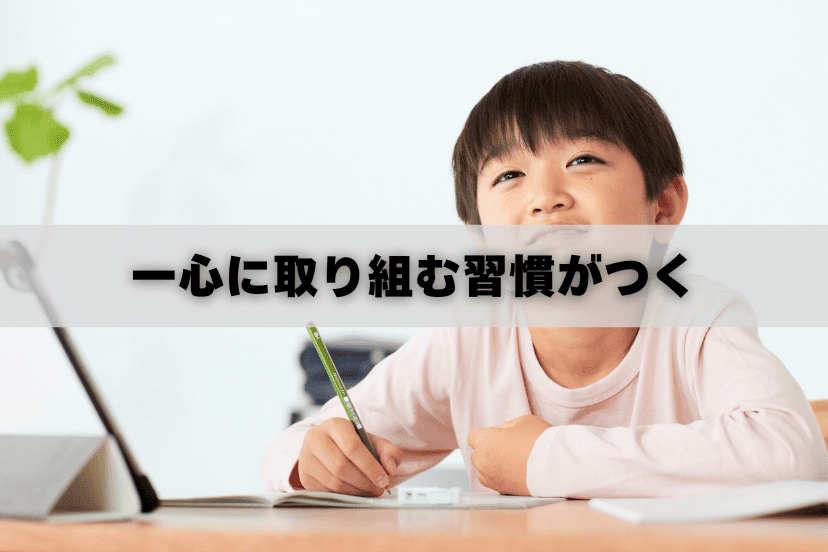
そろばんでは、珠を一つでも間違えて動かすと計算全体が狂ってしまうため、作業中に雑念が入り込む余地がほとんどありません。
たとえ周囲が少し騒がしくても、目の前の珠と数字に意識を一点集中しなければ正確に解くことができないのです。このように「今この瞬間にだけ意識を向ける」練習を日常的に繰り返すことで、自然と雑念を排除する力が育ちます。
近年注目されるマインドフルネス(現在に意識を集中する瞑想法)とも通じる効果があり、そろばん経験者の子どもは非経験者に比べて「作業中に気が散らない」と答える割合が高いという調査結果もあります。
情報や刺激があふれる現代では、集中中に余計な考えが浮かんで作業が中断されることが多く、雑念を抑えて目の前に没頭する力は非常に貴重です。そろばんはその力を自然な形で育ててくれるのです。
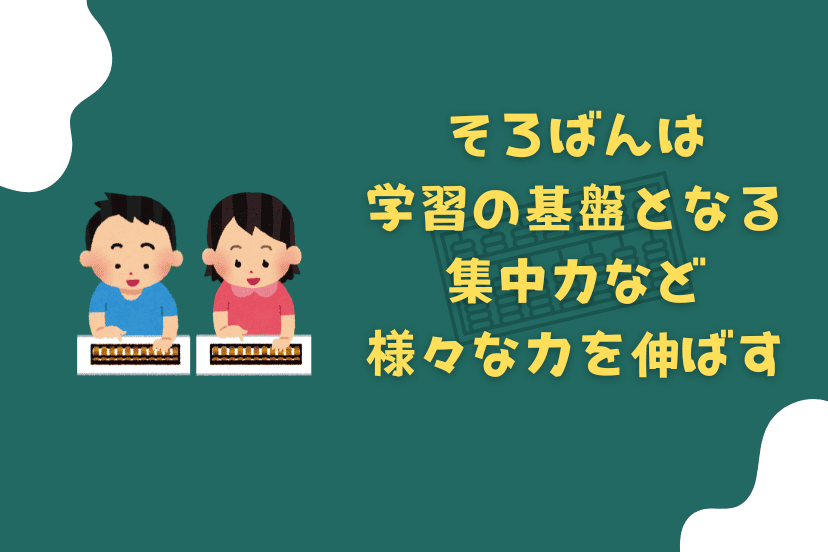
そろばんは単なる計算力を鍛える道具ではありません。
学習全般の基盤となる力を総合的に伸ばす習い事です。そろばんの練習では、制限時間内に正確な処理を繰り返すことで集中力や注意力が磨かれ、前頭前野と頭頂葉を同時に活性化させることで記憶力や論理的思考力も高まることが研究で示されています。
また、頭の中で珠を動かすイメージ暗算は内的な集中力やワーキングメモリを鍛え、検定や大会を通した成功体験は自己肯定感や忍耐力を育みます。
こうして培われた力は算数だけでなく、読解・作文・理科・社会といった他教科の学習にも波及し、将来にわたる学習意欲や学力の土台をつくります。もちろん、中学受験といった本格的な勉強にも良い影響を与えます。
そろばんは、子どもがこれからの時代を生き抜くために欠かせない「集中力」をはじめとする非認知能力をバランスよく育てる、非常に優れた教育法なのです。
オンライン学習というと、つい「集中力が続きにくいのでは?」と心配されがちです。
しかし、実は逆に集中力を伸ばしやすい環境が整っています。自宅で学ぶオンライン形式では、周囲に同年代の子どもがいないため他人の視線や進捗を気にする必要はありません。
「自分の課題にだけ意識を集中する」内的集中力が自然と養われます。
また、教室のように通学や待ち時間がないため、学習前後に気が散る要因が少なく、学習のスイッチを入れやすいのです。
さらに「ネットdeそろばん」では、マンツーマンと少人数制を組み合わせたハイブリッド形式を採用しています。
完全な個別指導だけでは緊張感が薄れやすく、逆に大人数では集中が途切れやすいという弱点がありますが、ネットdeそろばんでは講師の目がしっかり届きつつ、同じ時間に学ぶ仲間の存在が程よい刺激となるため、安心感と緊張感のバランスの中で集中しやすい環境が実現しています。
また、講師は一人ひとりの習熟度や性格に合わせて声がけや進行を調整してくれるため、集中力が途切れそうになったときも、適切に気持ちを切り替えながら学習を続けることができます。
このように、ネットdeそろばんは「周囲に惑わされず、先生の目が届く環境で、自分に合ったペースで取り組める」ため、集中力を高めたい子どもにとって最適な学習スタイルといえるのです。
まずは、お子さまが楽しんでそろばんを続けられそうか、無料体験で実感してみませんか? 初めてでも安心して参加できるよう、お子さんの学習状況に応じてスタートできる体験レッスンをご用意しています。
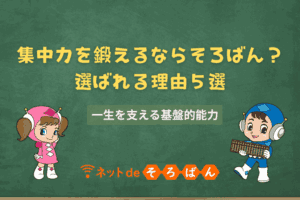
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます