\スグに読める/
\30秒で申込完了/
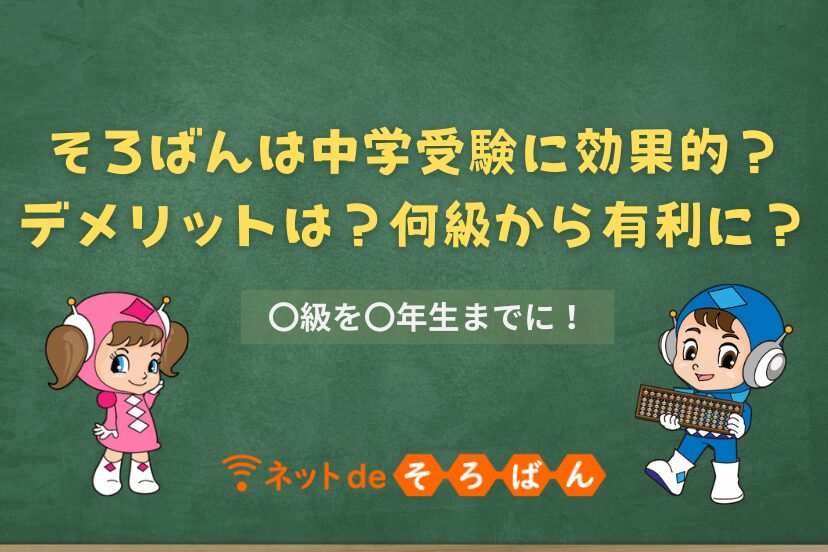


そろばんを学ぶことは中学受験にもプラスになるのでしょうか?
小学校受験などでは科目の勉強試験などはありません。しかし、6年経てばすぐに中学受験がやってきます。私立中学を目指すのであれば算数は必須科目です。
しかし、難関校になればなるほど、単純な計算では太刀打ちできるものではありません。果たしてそんな中で、計算がいくら早くなったところで有利になるのでしょうか?また、それゆえの弊害はないのでしょうか?
中学受験における、そろばんを習うことが効果的なのかということについて解説します。
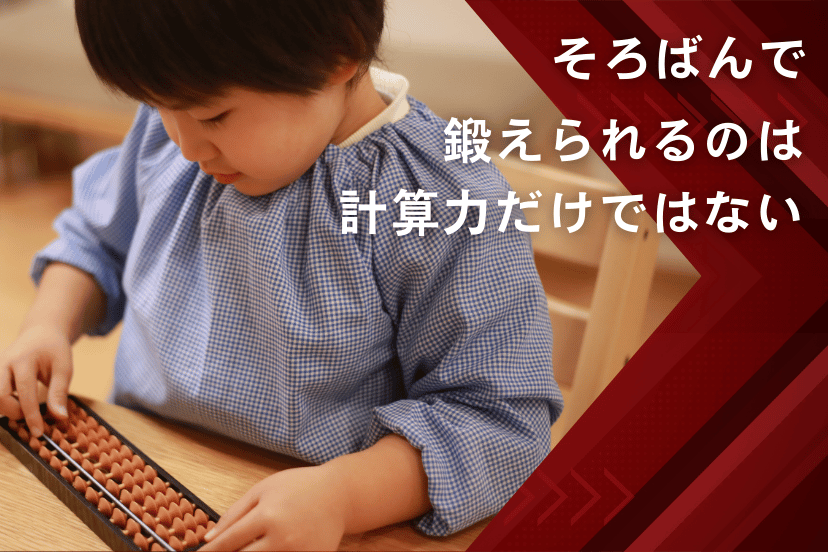
そろばんというと、どうしても数字に強くなるというイメージが先行してしまいます。しかし、そろばん教室で鍛えられるのは計算力だけではないということです。
そろばんを学ぶことにより、暗算処理速度だけではなく、集中力、記憶力、情報処理能力など、中学受験で求められる「自分で勉強する力」の基盤が育まれます。
中学受験で必要とされるのは「自分で考え、粘り強く学ぶ力」です。例えば長時間の試験で集中を切らさずに問題に取り組む持久力や、複数の条件を頭の中で整理して答えを導く論理性なども必要になってきます。
これらの能力を総合的に伸ばすことができるというのが”そろばん“です。実際に中学受験をさせたいという意識が高まっている一方で、そろばんへの意識も高まっています。
令和6年の習い事ランキングでそろばんは6位。近年はトップ10に入ることが多く人気が高まっています。(かつての定番「そろばん」が6位に 小学生の習い事ランキングに変化、中学受験も影響か)
どういった能力を伸ばすことができるかは、幼児教育にそろばんを取り入れるべき12の理由と効果を読んでみてください。
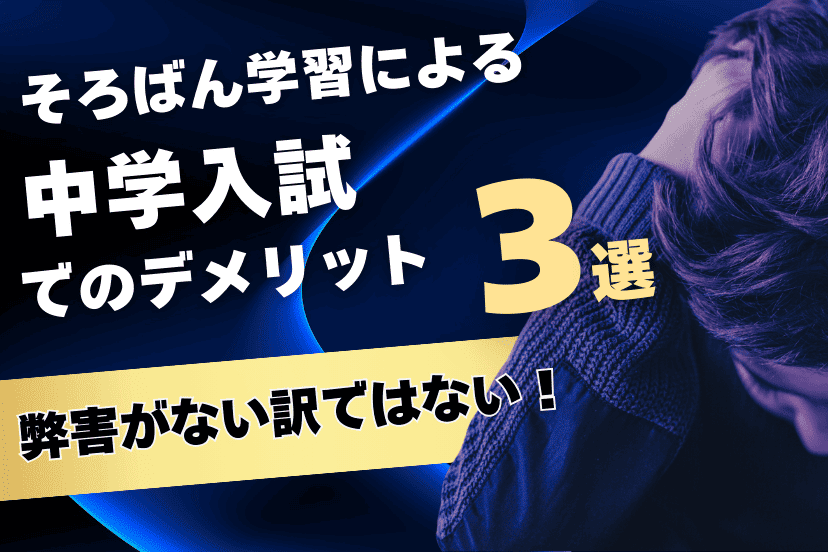
そろばんは確かに、暗算が得意になり数字に強くなるのは大きなメリットです。
しかし一方で、そろばん学習を続けることで中学受験において思わぬ落とし穴が待ち受けていることをご存じでしょうか。
実は、計算が速いがゆえに“工夫しなくなる力”や“書かない習慣”、さらには“思考型問題の苦手意識”といった弊害が生まれることもあるのです。
今回は、そろばんを武器にするためにあらかじめ知っておきたい、中学受験で注意すべき3つのポイントを詳しく解説していきます。
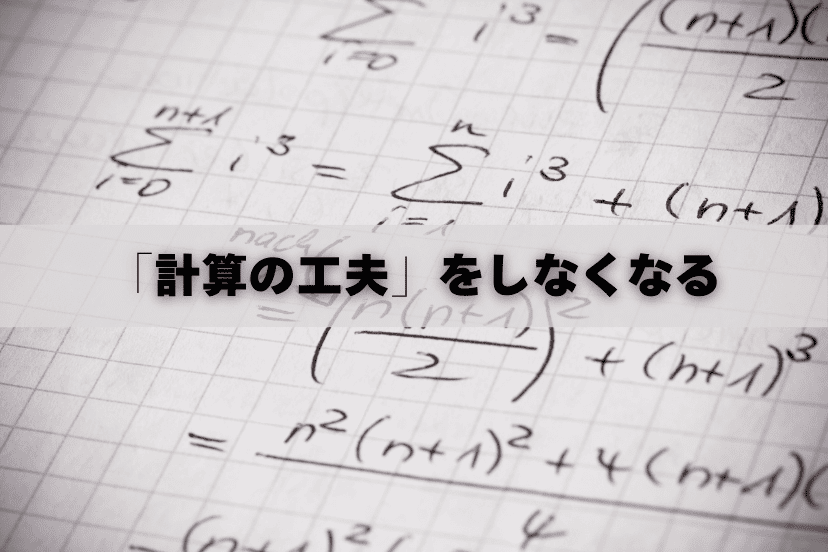
そろばんを長く学んでいる子どもは、暗算や筆算を使わずとも頭の中でスピーディーに答えを導けるようになります。これは大きな強みである反面、中学受験においては一つの落とし穴にもなり得ます。
中学受験の算数では、単純な計算問題だけでなく「計算の工夫」を問う問題が頻繁に出題されます。
例えば分配法則を活用したり、対称性を利用して計算量を減らすような問題です。しかし、そろばんに慣れている子どもは、そもそも計算に苦労を感じないため、わざわざ工夫する必要性を感じにくくなります。
結果として、工夫して効率よく解く練習が不足し、思考力を試される応用問題で不利になることがあります。
さらに、受験本番では制限時間の中で複雑な計算を大量に処理する必要があります。その際、工夫によって大幅に計算量を削減できる問題を暗算だけで解こうとすると、時間を浪費してしまうリスクもあります。
つまり、そろばんによる「速さの武器」が裏目に出て、工夫する思考の幅を狭めてしまう可能性があるのです。
中学受験においては「工夫して解く力」も同時に求められます。そのため、日常学習の中で意識的にバランスをとることが大切です。
具体的には、算数の学習時に「ただ解くだけ」で終わらせず、「別の方法で解けるか?」と問いかける習慣を持たせると効果的です。
例えば、分配法則を利用した解き方や、数のまとまりを見つけて計算量を減らす工夫を親子で一緒に確認してみるのも良いでしょう。
また、解答後に「どの方法が一番早かったか」「どの方法なら計算ミスを防げたか」と振り返ることも、考える力を育てる練習になります。
答えが合っていることよりも、その答えが導き出された流れを大事にしてみましょう。
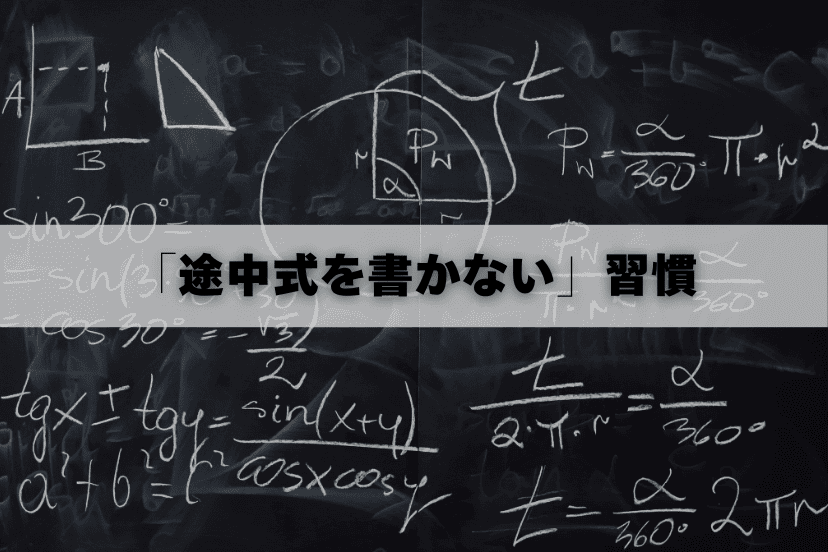
難関校、難関問題になればなるほど、答えはもちろん、答えが導き出された流れが大事になってきます。
そろばんをしていると、頭の中にそろばんがある状態になります。そのため、「途中式を書かない」習慣がついてしまいがちです。
そろばん学習では答えを出す速さが重視されるため、プロセスを丁寧に記録するという訓練はほとんど行われません。
その結果、中学受験本番で「答えが合っていても途中式が書かれていないために部分点がもらえない」あるいは「一見正解に見えるが検算できず失点する」という可能性もあります。
特に算数の入試問題では、解答欄に答えだけでなく途中式や思考過程を残すことが採点基準に含まれるケースも少なくありません。
つまり、そろばんで計算力を鍛えた子どもほど「答えを導く過程を他人に伝える力」が不足しやすいのです。
そろばんで計算力を身につけた子どもにとって、頭の中で答えを出してしまうのは自然な流れです。
しかし、中学受験においては「途中式を残すこと」が点数確保のためには重要です。
そのため、家庭学習や塾の演習では、あえて「途中式を書くこと自体を目的にした練習」を取り入れるようにしましょう。
例えば、簡単に暗算できる問題でも、必ず筆算や式で書き残すように声をかけることが大切です。また、テスト形式の演習では「答えが合っているか」だけでなく「解き方を採点者に伝えられているか」という視点で自己採点させると、書き方の意識が自然と高まります。
途中式を書く習慣は、一朝一夕では身につきません。日常の学習で繰り返し「見える形で思考を残す」ことを意識させることが、受験での減点を防ぐ最善の対策なのです。
答えが合っていることよりも、その答えが導き出された流れを大事にしてみましょう。
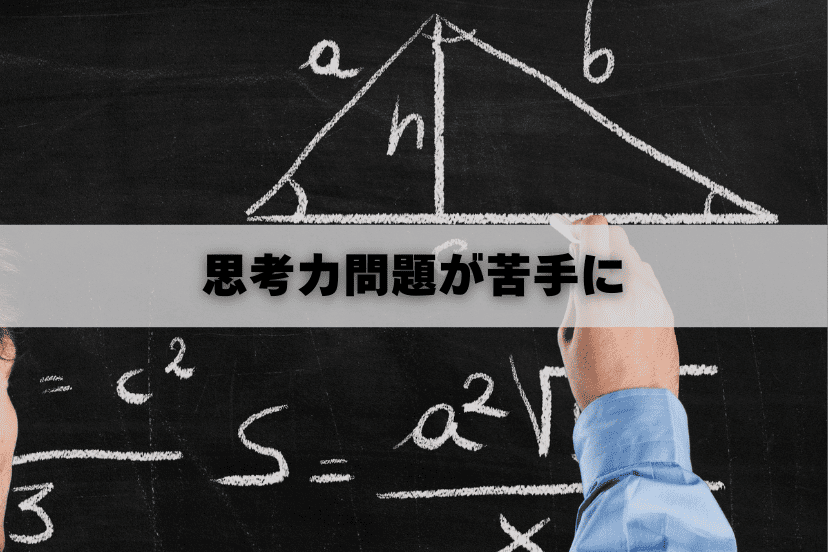
そろばんを学んでいると、四則演算はもちろん、複雑な数値処理も頭の中で素早くこなせるため、単純計算系の問題で大きなアドバンテージを発揮します。
しかし、中学受験の算数で頻出するのは、単なる計算問題だけではありません。長文の文章題や、図形の面積・体積を考えさせる問題、さらには数の規則性を見抜く思考型問題が多く出題されます。
こうした問題は「計算」よりも「状況を整理する力」「仮定を立てる力」「論理的に筋道を追う力」が必要とされます。ところが、計算が得意な子ほど「まず計算で解ける問題」に意識が向きやすく、自然と文章題や図形問題を避けてしまう傾向があるのです。
その結果、思考力を必要とする分野が苦手になり、得点のバランスが崩れるリスクがあります。
特に難関校では、全体の6〜7割が思考型の問題で構成されている場合もあり、計算力だけでは合格ラインに届かない可能性もあります。そろばんの強みを活かす一方で、思考力問題に取り組む姿勢を育てることが欠かせません。
計算力に自信のある子どもが思考力問題を避けてしまうのは自然な傾向です。しかし、中学受験ではむしろその逆、文章題や図形・規則性といった「考える算数」が合否を分けます。
そのため、意識的に思考型問題へ触れる機会を増やすようにしましょう。まず取り入れたいのが「図や表に書き出す習慣」です。
頭の中だけで処理しようとせず、与えられた条件を整理して図示することで、文章題や規則性の問題も解きやすくなります。
また、計算に直結しない問題でも「どの情報が必要か」を探す練習を繰り返すことで、論理的思考力が鍛えられます。さらに、塾のテキストや市販問題集の中から、敢えて図形や規則性の単元を優先して取り組む時間を確保するようにしましょう。
計算問題を短時間で片付けられる強みを活かし、その分の学習時間を思考型問題に回すよう意識すれば、バランスよく得点力を伸ばせます。
要は「得意な計算」に偏らず、「苦手な思考系」へ挑戦する姿勢を継続的に育てることが、受験に直結する最善の対策です。

珠算検定6級以上になると暗算分野が出てきます。この暗算が「右脳の活性化」につながると言われています。(そろばんはなぜ右脳開発に効果があるの?活性化する理由と根拠)
そろばん経験者は、頭の中で珠をイメージして動かしながら計算を進めるため、単なる数値処理ではなく「映像的記憶」「直感的処理」が鍛えられます。
京都大学の研究でも、熟練した珠算学習者は前頭前野と頭頂葉の結合が強化され、数的処理をイメージとして保持できることが示されています。これは左脳主体の論理的思考とは異なる右脳的な力であり、中学受験で頻出する図形や立体の把握、規則性の発見などに直結します。
例えば、立方体の展開図を頭の中で組み立てる問題や、文章題で条件を整理して場面を想像する力は、まさに右脳のイメージ処理が活きる場面です。
また、右脳が鍛えられることで「ひらめき型の解法」を導き出しやすくなり、時間制限のある入試本番でも大きな武器となります。つまり、そろばん学習は単なる計算力強化にとどまらず、右脳の働きを通じて受験算数に必要な空間認識力や直感的判断力を伸ばす可能性があります。
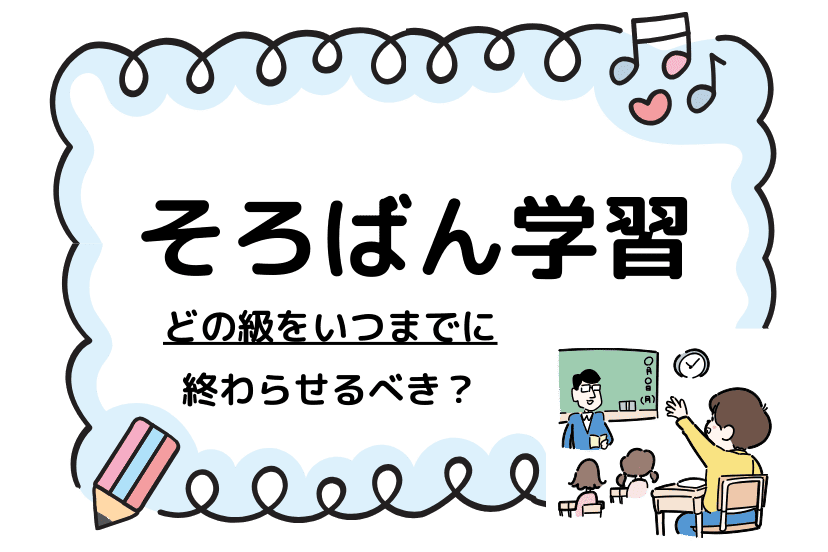
中学受験をする際に、そろばん学習の効果を最大限発揮させるためには、どの級をいつまでに終わらせるべきなのでしょうか?
中学受験を意識してそろばんを学ぶ場合、ひとつの目安となるのが珠算・暗算ともに3級以上の取得です。
多くの塾講師や先生が「3級で十分に受験に通用する計算力が身につく」と言っている事が多いです。それだけあれば、暗算力や数感覚の面でも実用的なレベルに到達できます。
実際、内申点や特技欄に記載できるのもおおむね3級以上からとされるケースが多いです。さらに、難関中学を目指すなら2級、可能であれば1級を小学校高学年までに取得しておくと安心です。
特に2級以上になると、小数や大きな桁数を含む複雑な暗算も可能になり、算数全般のスピードと正確性が一段と高まります。
タイミングとしては、小学校4年生までに3級合格を目標にすると、中学受験の準備と並行しやすく、その後は塾の勉強にシフトしても基礎力が落ちることはないでしょう。
余裕があれば小5の早い段階で2級取得を目指し、算数の計算分野で大きな武器を持った状態で受験勉強に臨むのが理想です。受験直前に新しい級を狙う必要はなく、小4〜小5の間に区切りをつけておくことがポイントになります。
そろばんを学ばせるベスト時期はいつ?
そろばんを学ばせるベストな時期は、数への興味が芽生える幼稚園年長から小学校低学年(1〜3年生)の段階とされています。ただし、これは子ども達個々によっても異なります。そろばん学習は何歳から始めるのが良いのか、注意点を別記事にて解説していますので参考にしてください。
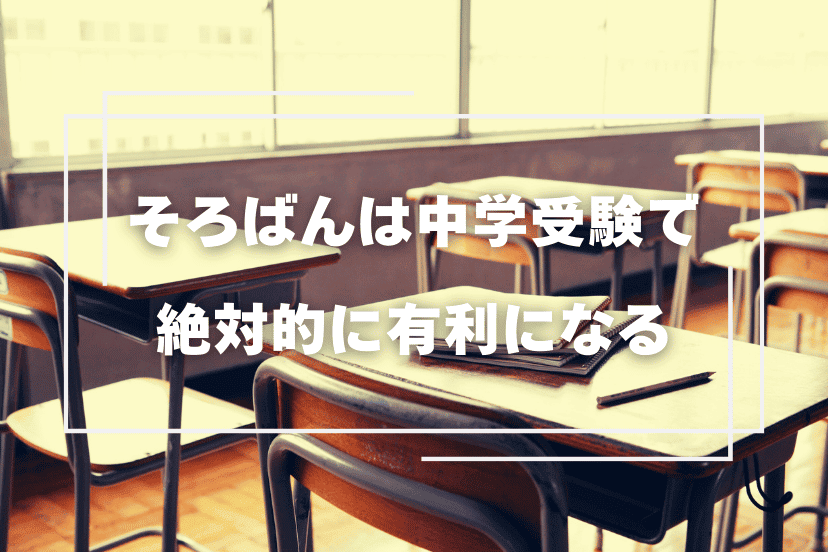
ここまで見てきたように、そろばん学習は単なる計算力が上がるだけではありません。中学受験に必要な幅広い力を養うことにつながります。
確かに、計算スピードが速いというだけでは難関校は突破できません。しかし、そろばんを通じて鍛えられる集中力や記憶力、右脳を使ったイメージ処理力は、文章題の読解や図形問題の把握に直結します。
また、条件を整理し筋道を立てる力は国語の論理的読解や理科の実験問題、社会の資料問題などにも活かされ、算数以外の科目でも効果を発揮します。
つまり、そろばんは「計算力」という一つの技能にとどまらず、「自分で考え抜き、最後までやり遂げる力」を育てる総合的な学習法なのです。注意すべき弊害を理解し、正しく補いながら続けていけば、そろばんは中学受験における絶対的な武器となり得ます。
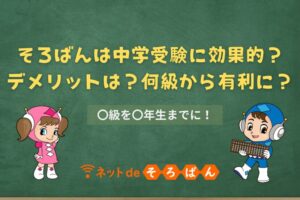
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます