\スグに読める/
\30秒で申込完了/
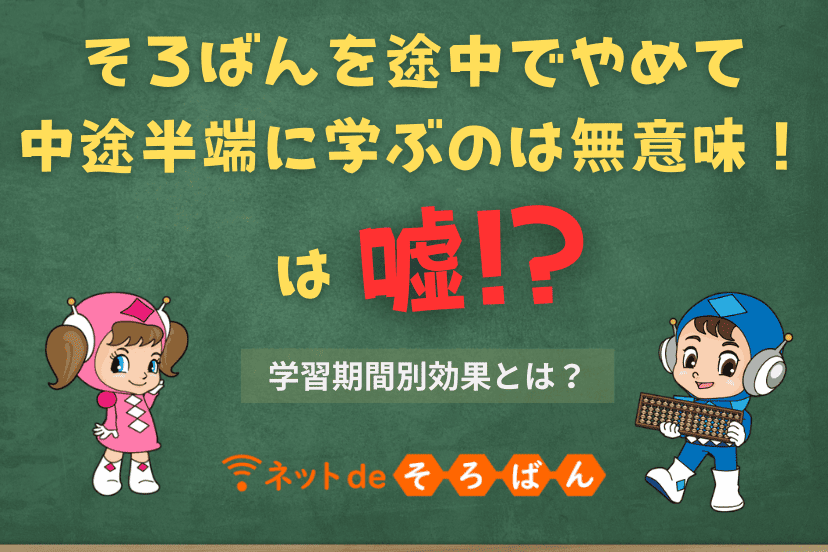


子どもの習い事として長年人気を集めるそろばん。
暗算力の向上や集中力、さらには右脳の発達にも良いと言われ、教育熱心な家庭を中心に幅広く支持されています。
しかし、「継続しないですぐやめてしまったらどうしよう」という不安もありますよね。また、いざ始めてみると「計算が早くなった気がするけれど、そろそろやめてもいいのかな?」と悩む時期が必ず訪れます。特に小学校高学年になると他の習い事や勉強との両立が難しくなり、途中でそろばん教室をやめる子どもも少なくありません。
そんなとき、多くの親御さんが心配するのが「中途でやめたら意味がないのでは?」という疑問です。
確かに、資格のように“合格”という明確なゴールがあるわけではなく、どの段階まで続ければ十分な効果が得られるのか分かりにくいのがそろばん学習の難しいところです。
せっかく時間とお金をかけて通わせたのに、効果が不十分ならすべて無駄になるのでは…と不安になるのも無理はありません。
では実際のところ、そろばんを途中でやめることは本当に無意味なのでしょうか。短期間の学習でも得られる力はあるのか、それとも一定レベルまで続けなければ意味がないのか。
この記事では、教育現場の声や専門家の意見、さらに実際にそろばんを習った人の体験談をもとに、そろばん学習を途中でやめることのメリット・デメリットを徹底的に解説します。
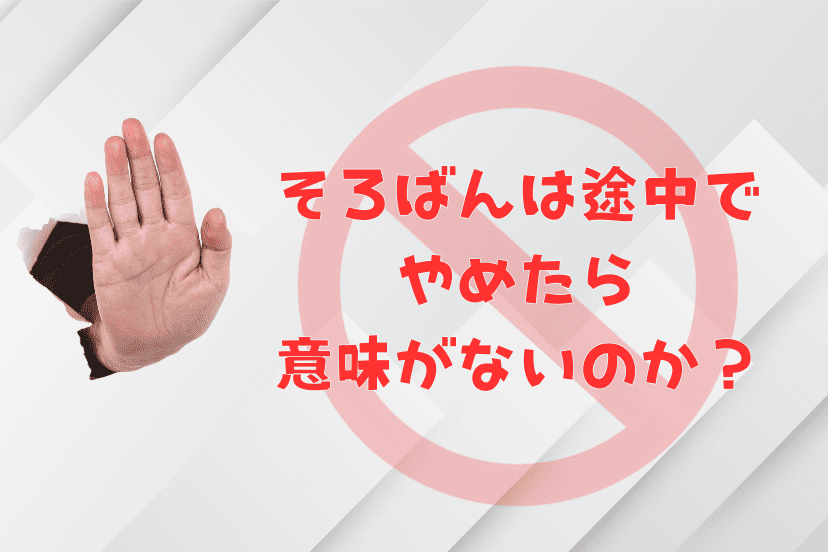
そろばんを途中でやめたら意味がないのかという疑問は、多くの親御さんが一度は抱く悩みです。
結論からいえば、そろばん学習は途中でやめても“まったく無意味”になるわけではありません。
なぜなら、そろばんを学ぶ過程で得られる暗算力や数への親しみ、集中力や記憶力のトレーニングといった効果は、学習の初期段階からすでに脳に刺激を与え、子どもの成長に一定の影響を与えているからです。
例えば、日本珠算連盟の調査でも、そろばん学習を1年程度経験した子どもは、未経験の子どもに比べて暗算のスピードと正確性が有意に高いという結果が出ています。
つまり短期間であっても基礎的な計算力や数感覚は確実に育まれるのです。
しかし一方で、珠算検定合格を目指す段階まで継続することで、暗算力の飛躍的な向上や、頭の中にそろばんを思い浮かべて計算する「イメージ暗算」の習得といった高度な力が身につきます。
これらは短期間ではなかなか習得できないため、途中でやめてしまうと十分な能力開発の前に学習が止まってしまうリスクもあるのは確かです。
したがって「まったく意味がない」というよりは「得られる効果の深さが変わる」と理解するのが正しいでしょう。

そろばん学習は、計算力や集中力の向上に加え、右脳と左脳のバランスの良い発達を促すといわれています。
特に、計算を繰り返す中で脳内に「珠(たま)」のイメージを思い浮かべ、頭の中だけで計算する「イメージ暗算」へと進化する過程は、短期間の学習では到達が難しい高度なスキルです。
このイメージ暗算を習得するには、珠算3級程度の反復練習と一定期間の継続が必要とされており、教育現場のデータでも2〜3年程度の学習を経て習得する子どもが多いことが報告されています。
途中でやめてしまうと、このイメージ暗算の段階に到達する前に学習が止まってしまい、暗算力や集中力、記憶力などの認知スキルが最大限に伸びきらないまま終わる可能性があります。
特に暗算力は、基礎計算の習得→スピードアップ→イメージ暗算という段階的な成長プロセスを経て初めて高いレベルに達するため、継続期間が短いほど得られる効果も限定的になるのです。
つまり、そろばん学習のより強い効果は、ある程度の年数と段階を踏んでこそ発揮されます。途中でやめると、どうしても“伸びしろ”が残ったまま終わってしまうことが、効果が薄れるといわれる大きな理由なのです。

そろばん学習で十分な効果を得るには、どの段階まで続けるべきなのかという疑問は、多くの親御さんが思っていることでしょう。
一般的に、そろばんの基礎計算力や集中力、数感覚の向上といった効果は、学び始めて1年程度である程度身につくといわれています。
実際、日本珠算連盟の調査でも、初級レベルでも計算スピードや暗算力は未経験者に比べて明らかな差が見られることが分かっています。つまり、短期間でも一定の効果は得られるのです。
しかし、珠算3級以上になると、足し算・引き算だけでなく掛け算や割り算も含めた複雑な計算をスピーディーかつ正確にこなせるようになり、さらに頭の中にそろばんの珠をイメージして計算する「イメージ暗算」が習得可能になります。
イメージ暗算が定着すれば、そろばんがなくても高速で正確な暗算ができるようになり、中学以降の数学や受験勉強にも大きな強みとなります。受験目的でも、そろばんを活かしたいという場合は、その辺りを1つの目安として考えると良いでしょう。
そのため最低でも2〜3年、可能であれば珠算3級合格レベルまでの継続をおすすめしています。
そこまで続ければ、そろばんをやめても計算力や集中力といった能力が長期的に活きる形で身につくため、時間や費用に見合う十分な効果が得られるといえるでしょう。
最低でも2〜3年、可能であれば珠算3級合格レベルまでの継続がベスト!
しかし、短期間だけのそろばん学習でも無駄にはならない。

そろばんを途中でやめてしまうデメリットは、イメージ暗算が習得できないことだけではありません。
まず挙げられるのが、集中力や忍耐力をトレーニングする機会を失うことです。
そろばん学習は単なる計算技術の習得にとどまらず、制限時間内に正確な答えを導き出すための集中力や、ミスを減らすための冷静さ、何度も反復練習を続ける忍耐力を自然と養うトレーニングでもあります。途中でやめてしまうと、こうした非認知能力の発達が十分に促されないまま終わる可能性があります。
また、小さな成功体験を積み重ねることが出来ないというのもデメリットでしょう。例えば珠算3級や段位に合格するまで続ければ、子どもは「努力すれば結果が出る」という達成感を得られ、自己肯定感の向上にもつながります。
しかし途中でやめると、この成功体験を味わう前に学習が終わってしまい、子どもが「自分はやり遂げられない」と感じてしまうことさえあります。
さらに、学習習慣の定着が難しくなることも見逃せません。
そろばんは毎日の練習が求められる習い事であり、その習慣が他の勉強やスポーツにも応用されることが少なくありません。早い段階でやめてしまうと、この良い学習習慣を身につける機会を逃してしまい、他の分野での継続力にも影響を与える可能性があります。

出来るだけ長く通わせたいけれども、時間や費用の問題、家庭の問題、子供の意向などで長期間続けることが難しい家庭も少なくありません。
学習期間を一か月・三か月〜半年・半年〜1年・1年〜3年・3年以上の5つに分けて、それぞれの期間でどのような効果が得られるのかを詳しく解説します。
短期間でも役立つケースと、長期継続で初めて得られる効果の違いを理解し、習い事の計画に役立ててください。
わずか一か月のそろばん学習では、計算スキルの劇的な向上は期待しにくいです。
ただし、数字に親しんだり、基礎的な計算の仕組みを理解するきっかけにはなります。特に幼児や小学校低学年では、指で珠を動かしながら計算する体験を通して数の増減を「目で見て」学べることが大きなメリットです。
(こちらに幼児教育としてそろばんを取り入れることで得られる効果についてまとめています。検討段階の人は是非参考にしてください。)
短期間でも「数字って楽しい」と感じられることは、将来的な算数への苦手意識を減らす意味で価値があります。
ただし、暗算力や集中力の大幅な向上には練習量が足りず、あくまで数字への導入期としての位置づけにとどまります。
3か月から半年続けると、足し算や引き算のスピードが徐々に上がり、簡単な計算を正確にこなせるようになります。
特に小学校低学年の子どもでは、この期間で数字に慣れ、算数への自信が芽生えることが多いです。
計算問題を繰り返す中で集中力や正確性も養われますが、まだ掛け算・割り算やイメージ暗算といった高度なスキルには到達しません。
学習の習慣づけや、数字に対するポジティブな感情を育てる段階としては有効な期間といえるでしょう。
実際、多くの人が「効果を実感し始めるのは3か月目以降」という調査結果もあります。
さらに、脳の前頭前野が活性化し、認知機能が改善したという高齢者の研究では、1日20分の簡単な計算を半年続けた結果、3か月後から前頭葉の機能が向上したことが確認されています
半年から1年になると、2桁以上の計算もスムーズに行えるようになり、学校の算数テストでも計算スピードで優位に立てることが増えてきます。
この時期には、暗算力の向上や集中力の持続時間の長さにも変化が見られるようになります。しかし、頭の中でそろばんをイメージして計算する「イメージ暗算」を習得するにはさらに継続が必要です。
したがって、この時点でやめると「計算力は伸びたが暗算力は中途半端」という結果に終わる可能性があります。
1年以上継続すると、そろばん学習の本当の効果が発揮されます。
特に2〜3年続けると珠算3級レベルに達し、掛け算・割り算を含む複雑な計算を高速かつ正確にこなせるようになります。
この段階でイメージ暗算も定着し、そろばんがなくても暗算が得意な子どもとして周囲に認識されることが多いです。さらに、資格合格や大会出場を通じて得られる達成感は、子どもの自己肯定感や学習意欲の向上にも大きく影響することでしょう。
3年以上続けると、計算力や暗算力に加え、集中力・忍耐力・自己管理能力といった非認知能力も高いレベルで身につきます。
段位取得レベルまで進めば、計算スキルはほぼ職業レベルになります。受験や将来の仕事にも活かせる一生もののスキルとなります。
また、長期間にわたり努力を継続した経験は、子どもの成長において非常に大きな成功体験となり、他の学習分野や人生のあらゆる場面でプラスに働きます。
そろばん学習を幼少期だけで終わらせるのではなく、ずっと続けるのも1つの選択肢です。
実は、今そろばんは、大人の脳トレや認知症予防にも効果があるといわれています。計算の際には指を使い、さらに頭の中で珠をイメージすることで脳の広い領域が同時に刺激されます。(大人のそろばんについてはこちら)
特に暗算は記憶力や集中力、情報処理能力を総合的に鍛えるため、脳の老化予防に役立つと報告されています。近年では高齢者向けのそろばん教室も増えており、楽しみながら脳を活性化させる手段として注目されています。
そのため、お子さんの健康寿命を延ばすという意味合いでも、そろばんを続けるのは役に立つと言えるでしょう。
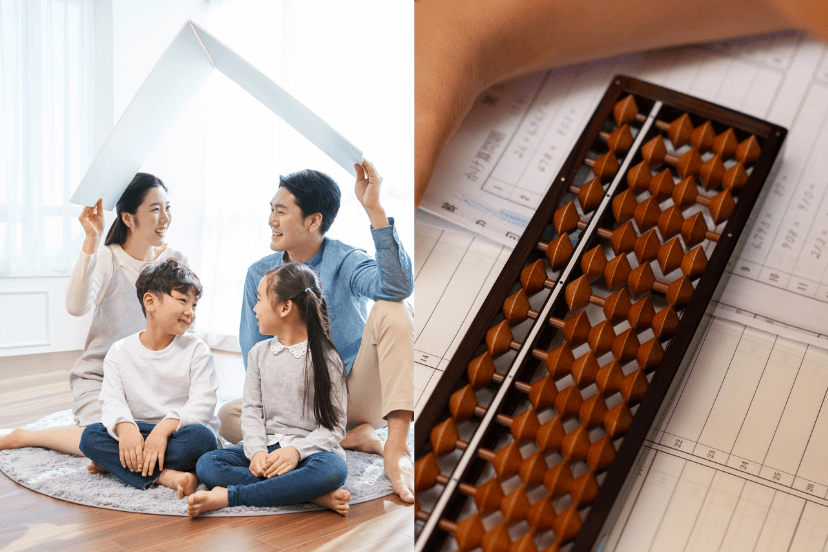
「習い事を始めるけれど、子どもがすぐにやる気をなくしてしまう…」
そんな悩みを持つ親御さんは多いものです。
では、子どもが飽きずに続けるために親や教室ができる具体的なサポートにはどのような方法があるのでしょうか。
ここでは、家庭での声かけの工夫から教室でのモチベーションづくりまで、実践的なポイントを解説します。
子どもが途中で投げ出してしまう原因の一つは、学習の成果を実感できないことです。
ご家庭では「速くなったね」「暗算ができたのすごい!」と小さな進歩を見逃さず、結果ではなく努力や過程を褒めることが大切です。
これにより子どもは「自分は成長している」という手応えを得られます。さらに、毎日5分だけの短時間練習を家庭に取り入れると、負担が少なく習慣化しやすいというメリットもあります。
教室側では、級位検定や教室内大会の開催が有効です。目標をクリアする達成感や、友達との競争は子どものやる気を引き出します。
さらに、タイムトライアル形式の練習やスコア更新シートなど、ゲーム感覚で挑戦できる仕組みを導入すると、学習が「やらされるもの」から「楽しいもの」へと変わります。
ご家庭と教室が連携し、子どもの様子を共有しながらサポートを続けることも重要です。
例えば、ご家庭で褒め、教室では先生が次の目標を明確に示すと、子どもは「自分は見てもらえている」という安心感を得られます。
こうしたサポートがあれば、そろばんは「やらされている勉強」ではなく「自分から続けたい学習」へと変わり、長期的な継続につながります。
時間の都合や家庭の事情、経済的な負担など外的要因でそろばんを続けられなくなるケースは少なくありません。
こうした場合は、オンラインそろばん教室の活用や月謝プランの見直しをしてみましょう。
オンライン教室なら送迎の手間がなく、家にいながらプロの指導を受けられるため、時間の制約を大きく減らせます。
また、月謝が高いことが負担になっている場合は、回数を減らしたプランや回数券制を導入している教室、今より安い教室を選ぶのも一つの方法です。
そろばん教室の平均月謝と教室の選び方をまとめていますので参考にしてみてください。
無理のない形で学習を続ける工夫をすれば、途中で諦めることなく、計算力や集中力の成長をしっかりと積み重ねていけます。
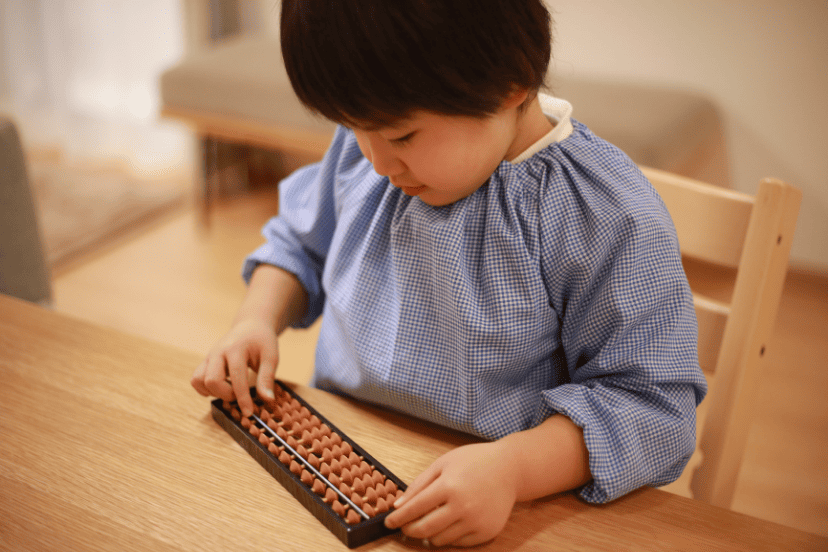
そろばん学習は、途中でやめても完全に無意味になるわけではありません。
短期間でも計算力や数への親しみは確実に身につきます。しかし、暗算力や集中力、忍耐力、そして「イメージ暗算」などの高度なスキルは、最低でも2〜3年、可能であれば珠算3級合格レベルまでの継続で初めてしっかりと定着します。
また、子どもがそろばんを嫌いにならず、長く続けられるようにするためには、ご家庭での褒め方の工夫や教室での目標設定などが欠かせません。
家庭と教室が連携し、小さな成長を見逃さずに認めてあげることで、そろばん学習は「やらされるもの」から「自分からやりたい学習」へと変わり、学びの質が大きく高まります。
時間や費用の制約で長期間の継続が難しい場合でも、短期集中で基礎的な計算力を身につけることは十分可能です。家庭の状況や子どもの性格に合わせた続け方を選び、そろばん学習を最大限に活かしていきましょう。
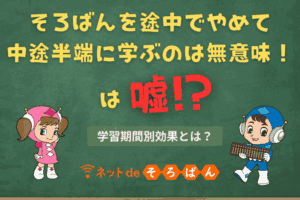
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます