\スグに読める/
\30秒で申込完了/
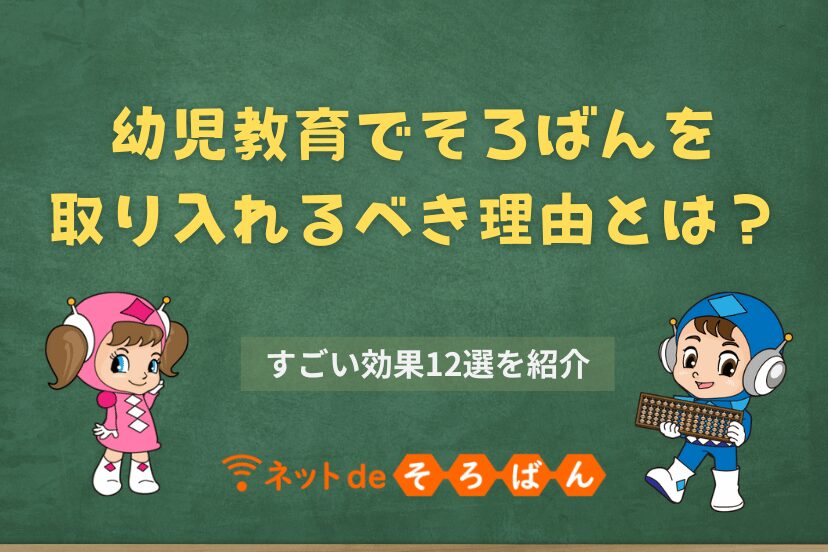


国際社会になり、より競争が激化しています。
そんな時流の中、「自分の子供に少しでもいい教育を受けさせてあげたい」と思っている親御さんも多いのではないでしょうか。
その答えの1つが幼児教育です。そして、幼児教育で何を学ばせるべきか、多くの方が悩むテーマです。
英語やプログラミングなど新しい習い事が次々に登場する一方で、昔ながらの「そろばん」が再び注目を集めているのをご存じでしょうか。
単なる計算道具と思われがちなそろばんですが、近年の研究では脳の発達や集中力、論理的思考力の向上にまで効果があることが明らかになってきました。
実際、幼児期からそろばんを始めた子どもは、数字への苦手意識が少なく、学習習慣や忍耐力の面でも優れている傾向が見られるといいます。
本記事では「幼児教育でそろばんを取り入れるべき理由」を12の効果に分けて徹底解説します。
なぜそろばんが今の時代に必要とされるのか、そしてどんな力が子どもの未来を支えるのか、わかりやすくお伝えします。
そろばんを幼児教育に取り入れるか悩まれている方は是非読んでみてください。

そろばんを学ばせるかどうか以前に、幼児教育をするメリットはあるのでしょうか?
多くの親御さんは幼児教育を単に小学校入学の準備としてとらえがちです。しかし、それだけのものではありません。
3〜6歳は脳の神経回路が急速に発達します。言語や感情、社会性の基盤が形づくられる極めて重要な時期です。カナダのマクマスター大学の研究によると、この時期の経験が将来の学力や社会性に大きな影響を与えることが示されており、教育を受けた子どもは認知能力・言語能力ともに未就学で教育を受けなかった子どもより高い成績を示す傾向があるとされています。
また、OECDのレポートでも、幼児期の教育経験がその後の学習意欲や学力格差の縮小に寄与することが指摘されています。
特に早期教育は認知能力だけでなく、忍耐力・協調性・自己管理能力といった非認知能力の向上にも効果があるといわれています。これらはテストの点数には直接表れないものの、将来の学業成績やキャリア形成に深く関係していることが、ハーバード大学の長期研究でも報告されています。
したがって幼児教育は「学力を高めるための早期スタート」というよりも、人間形成の土台を築き、将来の可能性を広げるための投資といえます。この視点からも、そろばんのように認知・情緒・社会性をバランスよく育てる教育が再評価されているのです。

ChatGPTなどの生成AIが登場し、「計算のスキルはもう不要なのでは?」「そろばんは時代遅れでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし近年、そろばん教育の価値は再び見直されています。その理由は、単純な計算力の習得だけでなく、脳の発達や学習習慣の形成に大きな効果があることが科学的に証明されてきたからです。
全国珠算教育連盟の調査によると、そろばん学習経験者は算数や数学だけでなく、文章読解や空間認識といった分野でも優れた成績を示す傾向が報告されています。これらの研究成果は、そろばんが単なる計算道具ではなく、子どもの脳と心の成長をバランス良く支える教育手段であることを裏付けています。
さらに、そろばんは「見える計算」から「頭の中での計算」へと発展する過程で、イメージ力や空間認識力を鍛えることができます。数字を単なる記号として覚えるのではなく、頭の中で立体的に操作する力を養うことで、算数以外の分野でも思考の柔軟性が高まるといわれています。
加えて、少しずつ問題を解き進める学習過程は小さな成功体験の積み重ねを可能にし、子どもの自己肯定感を高める効果も期待できます。
このように、子どもの頃からそろばんを学ぶことは単なる計算練習を超え、集中力・記憶力・論理的思考力・学習意欲といった多面的な成長を促す教育手段として、再び注目を集めているのです。

そろばんが単なる計算の道具にとどまらず、子どもの成長に欠かせない力を育むことがさまざまな研究で明らかになってきたことは解説させていただきました。
実際、そろばん学習経験者は算数や数学だけでなく、文章読解や空間認識といった幅広い分野で優れた成果を示す傾向があると報告されています。
幼児期にそろばんが選ばれる12の具体的な効果・理由をわかりやすく解説します。AI時代にもなお価値を持つそろばん教育の魅力を、ぜひ一緒に見ていきましょう。

幼児期にそろばんを始める最大のメリットの一つは、数字に自然と触れられ苦手意識がなくなることです。
小さな子どもにとって、数字は抽象的でイメージしにくい存在です。
1や2という記号を見ても、それが「量」や「順序」と結びつかないうちは、計算を学ぶことに抵抗を感じてしまいます。
ところが、そろばんでは指を使って珠をはじき、実際に数を「動かす」体験を通して、量や順序を視覚的・触覚的に理解できます。これにより、数字が単なる記号ではなく、意味を持った概念として子どもの中に定着していきます。
全国珠算教育連盟の報告でも、そろばん学習を続けた子どもは数字に対する抵抗感が少なく、算数の授業への苦手意識が低いことが示されています。特に幼児期は好奇心が強く、新しいことを遊び感覚で吸収できる時期です。
そろばんを通して数字と自然に触れ合う経験を積むことで、計算力の基礎だけでなく、数学的思考に対するポジティブなイメージが育まれます。
数字に親しみを持てることは、小学校以降の学習をスムーズにし、長期的には算数や数学への興味を高める土台にもなるのです。
そろばん学習は計算力を高めるだけでなく、脳のバランスの良い発達にも関係しているといわれています。
特に注目されるのが、右脳の活性化です。右脳はイメージ力や直感力、創造性を司る領域として知られており、この部分が発達することで思考の柔軟性や問題解決力が高まるとされています。
実際、2016年に発表された研究(Neural Plasticity following Abacus Training in Humans)では、そろばんを使った暗算訓練により前頭葉や頭頂葉の神経可塑性が向上し、脳の構造的な変化が確認されたことが報告されています。
そろばん学習者は、数字を視覚的なイメージとして右脳に記憶し、暗算時には左脳の論理的処理と右脳のイメージ処理を同時に活用していることが明らかになりました。
このような脳の両半球をバランス良く使う学習は、計算だけでなく読解力や図形認識、さらには創造的な課題への取り組みにも好影響を与えると考えられています。
幼児期にそろばんを始めることで、論理性と創造性を兼ね備えた思考力の基礎が自然に育まれていくのです。
詳しくはそろばんをすることによる右脳開発についてをお読みください。

幼児期にそろばんを学ぶ大きなメリットの一つが、集中力の向上です。
そろばん学習では、珠を正確に動かし、数をイメージしながら答えを導き出す過程において、自然と集中して取り組む時間ができます。
特に幼児期は注意力が分散しやすい時期です。しかし、そろばんのように手を動かしながら視覚と聴覚を同時に使う学習は、集中力を維持しやすいという特徴があります。
実際に、全国珠算教育連盟の調査では、そろばん学習経験者は計算速度や正確性だけでなく、課題への集中持続時間が長い傾向にあることが示されています。
また、海外のランダム化比較試験(RCT)でも、そろばん学習を8週間行った児童は、学習課題への集中力やワーキングメモリが統計的に有意に向上したと報告されています。
さらに、そろばん学習は短時間でも毎日継続することでより身に付きます。
少しずつステップアップする学習スタイルは、子どもに「学習する習慣」を自然と身につけさせます。幼児期にこの習慣が形成されることで、小学校以降の学習においても集中して取り組める基礎が築かれるのです。

そろばん学習の大きな特徴の一つが、イメージ力と記憶力を同時に鍛えられる点です。
そろばん学習では、暗算の段階に進むと、そろばんを頭の中に思い浮かべて珠を動かす「イメージ暗算」へとすすみます。
この過程で、数字を視覚的なイメージとして記憶し、頭の中で操作する力が自然と育まれていくのです。
2016年には、そろばん学習者は計算を行う際に脳の頭頂葉や前頭前野の活動が活発になり、視覚イメージを保持するワーキングメモリの機能が向上していることが確認されました。
さらに、全国珠算教育連盟の調査でも、そろばん経験者は文章暗記や図形認識といった数以外の課題においても高いパフォーマンスを発揮する傾向があると報告されています。
このように、そろばん学習は計算力の向上にとどまらず、脳のイメージ処理能力と記憶力を総合的に鍛えるトレーニングとしての価値を持っています。
幼児期からこの力を育むことで、算数以外の学習分野にも良い影響が期待できるのです。

幼児期の子どもにとって、学習はただ知識を得るだけでなく、成功体験を通して自信を育てることが大切です。
そろばん学習は、この「小さな成功体験」を日々積み重ねられる点で非常に優れています。
最初は簡単な足し算や引き算から始まり、慣れてくると桁数が増え、暗算へとステップアップしていきます。少しずつレベルが上がる仕組みは、子どもに「できた!」という達成感を与え、その積み重ねが自己肯定感の向上につながります。
教育心理学の研究でも、幼児期に小さな成功体験を積み重ねた子どもは、学習意欲が高く、新しい課題に挑戦する姿勢が育ちやすいことが示されています。特にそろばんは目に見える形で答えがわかりやすく、正解が得られるたびに子どもが自分の成長を実感しやすいのが特徴です。
さらに、全国珠算教育連盟の調査では、そろばん学習を継続している子どもは学習への前向きな態度や粘り強さが育ちやすいことが報告されています。これは、小さな成功を積み重ねる過程で「努力すれば成果が出る」という自己効力感が高まるためだと考えられます。
このように、そろばんは単なる計算練習ではなく、子どもの自信と学習意欲を育てる教育手段としての価値も大きいのです。

幼児期においてそろばんを続けられるかどうかは、いかに楽しみながら取り組めるかにかかっています。
そろばんは、珠をはじく音や手を動かす感覚が遊びの要素を持ち合わせており、学習を「勉強」というよりも「遊び」として捉えやすいのが大きな特徴です。
実際、教育心理学の分野では、幼児期において遊びを通した学習が好奇心を刺激し、学習意欲や集中力を高めることが数多く報告されています。
特にそろばんは、正解すれば達成感が得られ、少しずつ難易度が上がる仕組みのため、ゲーム感覚で取り組める点が子どもの興味を引きます。全国珠算教育連盟の調査でも、そろばん学習を始めた子どもの多くが「勉強嫌い」ではなく「もっとやりたい」という前向きな気持ちを示すことがわかっています。
さらに、遊び感覚で学べることは継続性の高さにもつながります。
幼児期は特に飽きやすい時期ですが、そろばんのように学びと遊びが融合した教材は、自然と学習時間を伸ばし、結果的に集中力や忍耐力の育成にも役立ちます。
このように、そろばんは幼児期の学びを楽しさと結びつけ、学ぶことへの好奇心と積極性を引き出す優れた教育手段なのです。
幼児期にそろばんを学んだ子どもは、小学校入学後の算数学習で大きなアドバンテージを得られます。
そろばん学習では、数の概念や計算の仕組みを視覚と手の動きを通して体感的に理解するため、数字を単なる記号として覚えるのではなく、「量」として把握する力が身につきます。
これにより、足し算や引き算だけでなく、繰り上がり・繰り下がりといった算数の基礎概念を直感的に理解できるようになります。
全国珠算教育連盟の調査でも、そろばん経験者は未経験者に比べて小学校低学年の算数テストで高い得点を示す傾向が報告されています。計算の正確さやスピードに優れ、文章題や応用問題にもスムーズに対応できるケースが多いとされています。
また、そろばん学習で培われる暗算力は、計算ドリルだけでは得られない数的処理能力を育みます。暗算を通して数を頭の中でイメージ化し、瞬時に計算する力は、算数だけでなく理科や家庭科といった他教科の学習にも波及効果をもたらします。
このように、幼児期からそろばんを学ぶことは、単なる先取り学習ではなく、小学校以降の学びをスムーズかつ自信を持って進めるための土台づくりになるのです。

そろばん学習は一見すると個別学習のように思われがちです。
ですが、実際には仲間や先生との交流を通じてコミュニケーション力を育てる場にもなっています。幼児期は、友達や大人との関わりを通じて言葉のやり取りや社会性を学ぶ重要な時期です。
そろばん教室では先生からの指導を理解し、質問したり、仲間と切磋琢磨したりすることで、自然と対話力や協調性が磨かれていきます。
教育心理学の研究では、学習活動におけるピア・ラーニング(仲間との学び合い)が子どもの社会的スキルや自己表現力の向上に効果的であることが報告されています。
そろばん教室での練習や検定試験に向けた取り組みは、仲間と目標を共有し、互いに刺激し合う良い機会となり、これが学習意欲の向上にもつながります。
さらに、先生とのやり取りを通じて「相手の話を聞く」「自分の考えを伝える」といった基本的なコミュニケーションの型が身につきます。これらは将来的に学校生活や人間関係の基礎力となります。
このように、そろばん学習は計算力の向上だけでなく、仲間や先生との関係性を通じて対話力・協調性・自己表現力を自然に育む教育の場でもあるのです。
幼児期にそろばんを学ぶことは、忍耐力や努力する姿勢などの非認知能力の育成にも効果があります。
(非認知能力とは、学力テストの点数には直接表れないものの、将来の学業成績や社会での成功に強く影響する力の総称。代表的なものとして、粘り強さ、自己管理能力、協調性、挑戦する意欲などが挙げられます。)
そろばん学習では、簡単な計算から始まり、徐々に難易度を上げながら繰り返し練習を行います。この過程で子どもたちは「すぐにはできない問題」に向き合い、試行錯誤しながら解法を身につけていきます。教育心理学の研究でも、このような適度な負荷と成功体験の繰り返しが忍耐力や努力する姿勢を育むことが確認されています。
さらに、全国珠算教育連盟の調査では、そろばん経験者は学習への持続力が高く、長期的な課題に対しても諦めにくい傾向があることが報告されています。これは「続ければできるようになる」という成功体験を重ねることで、自己効力感が高まり、困難な課題にも前向きに挑戦できる力が育まれるからです。
このように、そろばん学習は単なる計算練習を超え、将来の学びや生活に欠かせない非認知能力を自然に育てる教育手段としても価値が高いのです。

タブレット学習やAIの普及により、子どもたちが計算や情報処理を自分の手で行う機会は急速に減少しています。
しかし教育学や認知心理学の研究では、手を動かしながら考えることが思考力の発達に深く関わっていることが繰り返し報告されています。
そろばん学習は、まさにこの「手を使って考える力」を育てる代表的な教育手段といえます。
そろばんでは、指先で珠をはじきながら計算を進めます。この動作は単なる作業ではなく、脳の前頭前野や頭頂葉を活性化させ、数字の意味や量的な関係を理解する過程と結びついています。
実際、そろばん学習を続けた子どもは、暗算を行う際に右脳のイメージ処理と左脳の論理的処理を同時に活用していることが脳科学の研究で確認されています。
こうした手と頭を連動させる学習は、デジタル機器の操作のような受動的な学びでは得られない、自ら考え、判断し、答えを導き出す力を育てます。特に幼児期にこの力を養うことで、将来の論理的思考力や問題解決力の土台が形成され、AI時代に求められる創造的な学びへとつながるのです。
AI時代に必要とされるそろばんで伸びる7つの能力についてこちらの記事で説明しています。合わせてご参照ください。

幼児期の習い事選びでは、教育効果だけでなく費用の負担も保護者にとって重要です。
その点でそろばんは、ピアノや英会話、プログラミングといった習い事に比べて月謝が安く、全国平均でも他の習い事の半額以下に収まることが多いです。
それでいて得られる効果は計算力の向上だけでなく、集中力、記憶力、論理的思考力、さらには非認知能力の育成にまで広がります。
特に暗算力や数的処理能力は、小学校入学後の算数学習に直結するため、学習塾に通う前の基礎づくりとしても非常に効率的です。
さらに、費用が抑えられる分、保護者はそろばんと並行して水泳や英語、スポーツ教室など他の習い事にも投資できるというメリットがあります。1つの習い事に大きな費用をかけず、複数の経験をバランスよく積ませることができます。
このように、そろばん学習は家計に優しく、しかも多方面の能力を伸ばせる費用対効果の高い教育手段として、多くの家庭に選ばれているのです。
そろばん教室の平均月謝と教室の選び方はこちらにまとめています。
そろばん学習は計算力を鍛えるだけでなく、論理的思考力や問題解決力の基礎形成にも役立ちます。
そろばんは数字の組み合わせや手順を考えながら解答を導くプロセスが伴い、自然と効率的な解き方や工夫を考える習慣が身に付きます。
近年の研究でもこれらの効果が裏付けられています。例えば、2020年のレビュー論文 (A Review of the Effects of Abacus Training on Cognitive Functions and Neural Systems in Humans) では、そろばん訓練が算数の計算能力、ワーキングメモリ、数的処理能力を向上させる可能性が高く、前頭葉から頭頂葉および後頭、側頭葉にわたる脳の機能的・構造的変化を伴うと報告されています。
さらに、2019年の The Journal of Neuroscience に掲載された研究では、AMC訓練を受けた子どもたちは、視空間ワーキングメモリ(VSWM)が強化され、訓練前後で前頭部・頭頂部・後頭部など複数の脳領域の活動に変化が確認されました 。
幼児期の習い事としてそろばんを選ぶ家庭は増えていますが、実際に始めるとなると「何歳から始めるのが良いのか」「どんな教室を選べばいいのか」といった疑問が多く寄せられます。
そろばんは計算力だけでなく、集中力や論理的思考力、さらには学習習慣まで育てる効果が期待できる一方で、スタートのタイミングや環境によって子どものモチベーションや成長の度合いが大きく変わります。
そこで幼児期にそろばんを始める際の注意点をわかりやすく解説します。これからそろばんを習わせたいと考えている保護者の方が、安心して一歩を踏み出せるような具体的な指針をお伝えします。
そろばん学習を始める時期として多くの専門家が目安とするのは、4〜6歳の幼児期です。
この時期は脳の発達が特に活発で、新しい情報を吸収する力が非常に高いとされています。教育心理学の研究でも、幼児期に指先を使った学習体験を積むことが数概念の理解や認知機能の発達に好影響を与えることが報告されています。
そろばんはまさに指先の動きと数字の概念を結びつける学習であり、幼児期に始めることで脳の発達と結びついた深い学びが可能になります。
ただし、すべての子どもに同じ年齢で始めることが最適とは限りません。
数字への興味や手先の器用さ、座って学習に取り組める集中力などは個人差が大きいため、子どもの発達段階を見極めることが重要です。早く始めすぎて「わからない」「できない」という経験が続くと、学習意欲を失う原因にもなりかねません。
そのため、多くのそろばん教室では体験レッスンを通して子どもの適性や興味を確認し、保護者と相談しながら開始時期を決めています。焦らず子どもの成長を見守り、自然なタイミングで学びを始めることが、長く続けるための第一歩です。
実際に、そろばんを何歳から学ばせるか迷われている方はこちらの記事をご確認ください。
そろばん教室と一口にいっても、その指導スタイルやカリキュラムは教室ごとに大きく異なります。
ある教室は競技大会への参加を目標にスピードや正確性を徹底的に鍛える一方で、別の教室は幼児が楽しみながら学べるようにゲーム感覚の教材やカードを取り入れ、学習への興味を育てることに重点を置いています。
どちらのスタイルにもメリットがありますが、幼児期に大切なのは「数字への親しみ」と「学ぶことへのポジティブな感情」を育むことです。
教育心理学の分野でも、幼児期の学習では達成感や楽しさが学びの継続に大きな影響を与えることが報告されています。
特に初めての習い事では、厳しすぎる指導は子どもの意欲を下げてしまうリスクがあるため、子どもが楽しみながら成功体験を積める環境を選ぶことが重要です。
また、カリキュラムの進め方も確認しておくべきポイントです。個別指導で一人ひとりのペースに合わせる教室もあれば、グループ形式で仲間と競い合いながら学ぶ教室もあります。
体験レッスンに参加して、子どもの性格や学習スタイルに合った指導方針を見極めることが、長く続けられる教室選びの鍵となります。
そろばん学習を長く続けるためには、費用と通いやすさの両面をしっかり考慮することが欠かせません。
習い事は継続することで効果が発揮されるため、保護者にとって無理のない料金設定であることが第一条件です。
また、通いやすさも長続きするかどうかを大きく左右します。送迎に時間がかかると親子双方にとって負担が増え、結果として学習の継続が難しくなることもあります。
自宅や幼稚園・保育園、小学校から近い教室を選ぶことで、生活リズムに無理なく組み込むことができます。最近ではオンラインそろばん教室も増えており、送迎が難しい家庭や地方在住の家庭にとって選択肢が広がっています。
費用面と通いやすさを事前にしっかり確認し、家庭の生活スタイルに合った教室を選ぶことが、子どもの学びを長期的に支えるための重要なポイントです。
そろばん教育は、かつての「計算道具」というイメージを超え、脳の発達・集中力・記憶力・論理的思考力・非認知能力といった幅広い分野に好影響を与えることが、多くの研究や教育現場の経験から明らかになっています。
特に幼児期は脳が柔軟で新しい刺激を吸収しやすい時期であり、このタイミングでそろばんを取り入れることは、子どもの将来の学習意欲や問題解決力の土台を築くうえで大きな意味を持ちます。
また、そろばんは費用面の負担が比較的少なく、家庭学習や他の習い事との両立もしやすい点で、保護者にとって現実的で始めやすい教育手段といえます。
数字への苦手意識を和らげ、学ぶことを楽しむ姿勢を育てることで、子どもは自ら考え挑戦する力を自然に伸ばしていきます。
幼児期からそろばんを学ぶことは、単なる習い事にとどまらず、これからの時代に必要な力を多面的に伸ばしてくれる投資です。
将来、子どもが自信を持って学びのステージを進んでいけるよう、ぜひ一度、そろばん教育の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。
そろばん教育に興味がある保護者の方も多いことでしょう。
ここでは、幼児期からそろばんを習わせたいと考える方が特に知りたいよくある質問とその答えをまとめました。
学習効果、教室選びのポイントなど、導入前に押さえておきたい情報をわかりやすく解説します。
一般的には4〜6歳が目安といわれますが、数字への興味や集中力の有無など、お子さまの発達段階に合わせて始めるのが大切です。
はい。そろばんは計算力だけでなく、集中力・記憶力・論理的思考力・非認知能力の発達にも効果があることが報告されています。特に暗算力の向上は、算数だけでなく理科や読解力にも良い影響を与えるとされ、幼児期からの脳のバランスの良い発達に貢献します。
一般的には週1〜2回の通学と、家庭での10〜15分程度の復習を半年以上続けることで効果が実感しやすいといわれます。継続して学ぶことで計算力だけでなく集中力や忍耐力も身につき、小学校以降の学習習慣の定着にも役立ちます。
指導スタイルやカリキュラム、先生との相性が重要です。体験レッスンに参加して子どもの反応を確認し、楽しく続けられる環境かどうかを見極めましょう。進度が早すぎる教室よりも、子どもの成長に合わせて段階的に学べる教室が理想です。
市販の教材やアプリを活用すれば独学も可能ですが、最初は正しい指使いや暗算のコツを身につけるために教室の指導を受けるのが安心です。
通学型と比べても遜色ない効果が期待できます。送迎の手間が省け、地方在住の家庭でも学べるのがメリットです。
一度身につけた暗算力は自転車の運転のように長期間維持されやすいといわれています。
そろばんは1回あたりの学習時間が短く、家庭学習の負担も少ないため学校の勉強との両立は十分可能です。むしろ集中力や学習習慣が育つことで他教科の成績にも良い影響を与えるケースが多いです。
そろばんで育つ暗算力・論理的思考力・集中力は、AI時代でも汎用性の高いスキルです。数学的センスや問題解決力の基礎を築き、社会に出ても役立つ力として評価されています。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます