\スグに読める/
\30秒で申込完了/
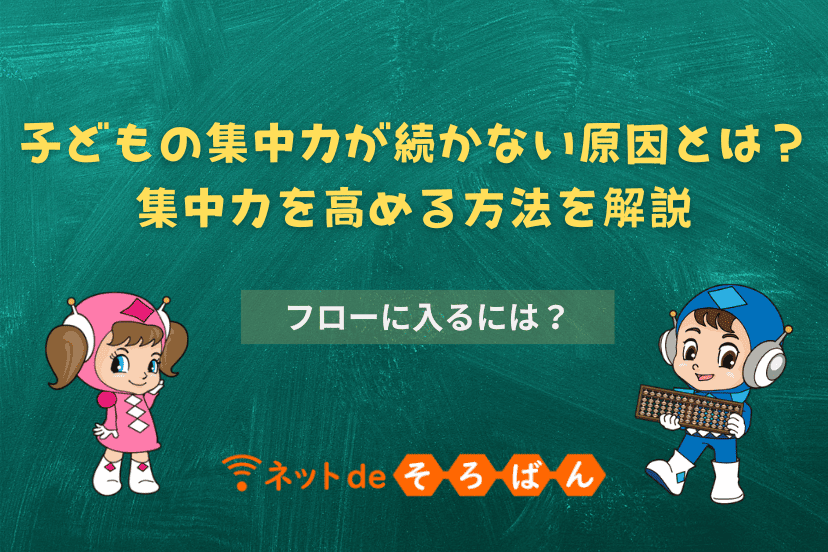


「うちの子、すぐ気が散ってしまう…」
「集中して勉強できるのは最初の数分だけ…」
そんな悩みを感じる親御さんは多いものです。ですが、子どもの集中力は“性格”や“才能”ではなく、家庭の環境や日々の習慣によって大きく変わります。
集中力が続かないのは、脳の発達や生活リズム、環境の刺激が関係していることもあります。つまり、少しの工夫で、集中しやすい時間を少しずつ伸ばしていくことができるのです。
本記事では、子どもの集中力を育てるための家庭での環境づくりや、日々の声かけの工夫、安心して取り組める学習リズムの作り方をわかりやすく解説します。
お子さまが「やってみたい」と思える時間を増やし、「できた!」と笑顔になれるきっかけを、家庭から育てていきましょう。

集中力とは、興味がある対象に注意を向け続ける力です。子供の集中力には年齢差があり、環境などの要因で大きく変わります。
まずは子どもの集中力の目安や理由を知り、無理のない習慣づくりを意識することが大切です。
親子でいっしょに取り組むと、やる気のスイッチも入りやすくなります。
子育ては親の行動で変わる場面が多いため、お子さまのタイプを理解し、フォローを重ねていくことが大切になります。
子どもの集中力の目安を知ることで、家庭学習の計画が立てやすくなります。よく使われるのが「年齢+1分」という目安です。例えば6歳なら7分程度です。
この短い時間でも十分な学びになります。まずは短い集中を積み重ねることを意識します。
この目安は脳の発達段階と関係しています。年齢が上がるほど少しずつ集中できる時間が伸びます。
初めのうちは集中する目標時間を短い設定にすることが、お子さんの安心につながります。
タイマーを活用して短い区切りをつくり、休憩をはさむと効果的です。授業や家庭学習のルーティン化も集中のスイッチづくりに役立ちます。
お子さまができたことを具体的に褒めることで自信とやる気が育ちます。
算数の教材など短時間で取り組めるものは集中力を鍛えるトレーニングにぴったりです。興味に合わせて、ゲーム感覚で始めると親子で続けやすいです。

子どもの集中力は幼児期に伸びやすいと言われています。短い時間でも、脳には良い刺激となり、発達を支える重要な体験です。
遊びや読み聞かせは、学びの土台を育てる時間になります。絵本は語彙力と想像力を育み、新聞の写真などは関心を広げるきっかけになります。親子でいっしょに楽しむと集中力が続きます。
幼児期はフロー状態に入りやすく、積み木やおままごとのような遊びで深く集中することがあります。設定時間は5分など短い設定で十分です。
無理に伸ばすより、できたことをいっしょに喜ぶことが大切です。
周囲を少し片づけるだけでも環境が整い、集中力が続きます。生活習慣も集中力の基盤になるため、睡眠や食事のリズムを整えることは大きな意味があります。
子どものタイプに合わせた工夫が効果を高め、成功体験が積み重なれば「できる」という感覚が成長につながっていきます。
子どもの集中力は小学校の経験でも大きく伸びます。
一方で授業時間が四十五分と長くなるため、家庭でのサポートが必要になります。
宿題では「準備→学習→休憩」の流れを意識すると、集中力が持続しやすくなります。学校の先生の指導と家庭のフォローがかみ合うと、習慣的に学習できるようになっていきます。
小学生は科目ごとに、集中できるものと苦手なものとに分かれます。
苦手科目になりやすい科目の一つに算数がありますが、手を動かす課題と相性が良く、読む・書く・考えるを交互に取り入れると集中しやすくなります。
最初は簡単な問題で成功させ、少し難しい問題で挑戦する流れをつくるのもポイントです。
お子さまのペースに合わせた環境づくりを意識すると集中力は着実にアップします。

子どもの集中力が低下する原因は、一つではありません。環境や習慣、心理的な要素が重なります。また年齢やタイプによっても違いが出ます。
ここでは主な原因を整理し、具体的な対策方法を順に解説します。
家庭での環境づくりとフォローで、集中力は必ず伸びます。親子でいっしょに見直していきましょう。
子どもの集中力は、近くにある刺激に左右されます。テレビやスマホは、強い光と音でお子さんの注意を奪います。テレビの電源は切り、スマホは別室に置きましょう。
机の上が散らかると、目と心が落ち着きません。宿題の途中で別の映像を見てしまうと、集中のスイッチが切れてしまいます。
テレビやスマホ、タブレットを見せる時間を、絵本の読み聞かせに置き替えると、語彙力と理解力が育ちます。お子さんが関心を持った新聞の写真を使って会話を始めると、学びに繋がります。
整った環境は、学習の土台です。まずは机とその周りの環境を整えましょう。
子どもの集中力は、その時の感情よって左右されます。
苦手なことが続くと、「またできないかも」という不安がふくらみ、算数の文章題などが出てきた時に最初から身構えてしまうことがあります。
結果だけを責められる経験が重なると、自信が下がり、やる気のスイッチも入りにくくなります。
ですが、失敗は成長の材料です。そこで、最初は「必ず解ける一問」を選び、小さな成功体験から始めることが大切です。
「できた」という実感が積み重なると、自然と次の課題にも挑戦したい気持ちが湧いてきます。
目標は小さく具体的にして、五分以内で終えられる課題にすると安心できます。
その上で、学校の先生の声かけと家庭でのフォローがかみ合うことで、お子さんの気持ちが整いやすくなります。うまくいった過程を言葉で褒めることは、お子さまの自信を育てる大切なサポートです。
また、お子さまのタイプに合う教材を選ぶことで、集中の入口が広がります。
手を動かす体験や、ゲーム性のあるトレーニングは「楽しい」と感じながら学べるため、思考力のアップにもつながります。
小さな達成がひとつ増えるたび、「次も頑張りたい」という前向きな集中力が育っていきますよ。
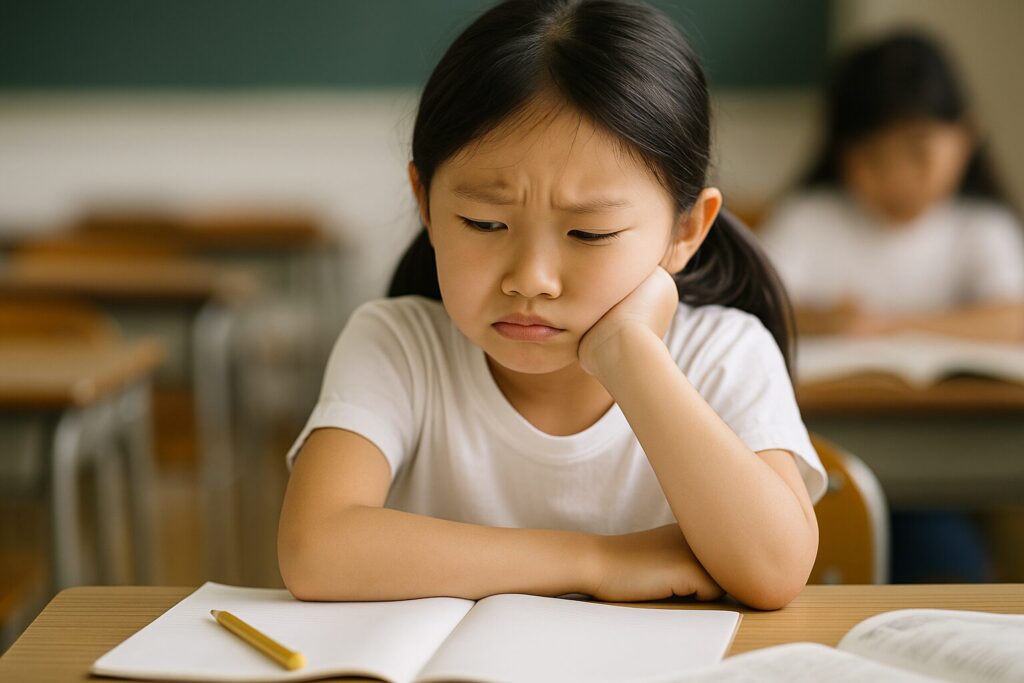
子どもの集中力は、生活リズムと連動します。
就寝が遅かった日は、学校の授業中にぼんやりしてしまうことがありますし、朝食を抜くと脳のエネルギーが足りず、注意を向ける力が弱くなります。
また、長時間の動画視聴は脳を強い刺激で疲れさせてしまい、結果として集中が続きにくくなることもあります。
まずは、起きる時間と寝る時間を整えることが大切です。
学習は食後しばらくしてから短い時間で始め、少し休憩してから再開する流れがスムーズです。短い時間でも、集中することの積み重ねが、持続力の土台になります。
さらに、不安や緊張などの心理的な状態も集中力にとってマイナスです。
宿題の量や内容が難しすぎるときは、調整したり、一緒に計画を考えてみたりすることも必要です。
心配ごとは言葉にすることができると軽くなるため、お子さんの話を聞く時間をつくってみてください。
親子で一日の流れや目安を共有できると、安心して取り組むことができます。
無理のない習慣が身につくと、子どもの集中力は少しずつ戻り、伸びていきます。
子どもの集中力は、安心感の上に育ちます。
叱責して席に座らせても、学びは深まりません。指示が多すぎると、思考は止まってしまいます。
また先に答えを与えてしまうと、自分で考える力が育ちません。行動を急かす声は、集中の敵になります。まずはできた一歩を認めましょう。
勉強に集中する時間の目安は、年齢で決めていきましょう。「年齢+1分」で十分です。目標は低く設定し、達成することで自信が芽生え始めます。
学習の最後には、良かった点を言葉にして振り返ることで、安心感が積み上がり、集中力が自然と続くようになります。
子どもの集中力は、生まれつきの能力だけで決まるものではありません。「夢中になれる時間」をどれだけ積み重ねているかが、大きな違いになります。
お気に入りの遊びに没頭して、呼ばれても気づかない。そんな姿こそ、集中力が育っている証です。
ここでは、集中力が高い子の共通点と「フロー状態」について、わかりやすく解説します。

集中力が高い子に共通して見られるのが、物事に対して「なんでだろう?」と心が動く場面が多いことです。好奇心は、学びのエンジンのような存在で、やる気と注意力を自然と引き出してくれます。
例えば、ブロックを組み替えながら形の変化に気づいたり、絵本の細かいイラストをじっと見つめたりする時間があると思います。
どれも「もっと知りたい」という気持ちが根っこにあります。
また、好奇心がある子は、失敗した時にも「なぜうまくいかなかったんだろう?」と考える力が育ちやすく、諦めにくいという特徴があります。
自分で試行錯誤を繰り返すことで集中力が続き、気がつけば長い時間没頭できることも多いです。
親ができることは、「頑張りを褒める」だけでなく「興味を持ったことに共感する」ことです。
「それ楽しそうだね」
「やってみたくなったんだね」
と声をかけると、お子さまの探究心がさらに育ちます。このサイクルが続くことで、集中力は自然と伸びていきます。
集中力が高い子は、周囲の変化にふり回されず、自分のやっていることに意識を向け続ける力があります。
この「切り替え力」は、もともとの性格だけでなく、日々の体験から育つ力です。
例えば、多少周りがざわざわしていても、読書や工作を続けられる場合があると思います。これは、心の中で「集中力の守備」をしている状態です。気になる音や動きをシャットアウトできると、学校でも家庭でも気持ちを落ち着けて学べるようになります。
この力を育てるには、環境を整えすぎないこともポイントです。あまりにも静かで完璧な環境でないと集中できないと、実際の場面で苦労します。
「誰かが歩いている音」や「物音が少し聞こえる場所」で取り組む経験も役に立ちます。

フロー状態とは「夢中になりすぎて時間の感覚が薄れる状態」を指します。
子どもが静かに黙々と遊んでいたり、顔を近づけてパズルに取り組んでいる時がありませんか?
それがまさに集中のピークです。フロー状態の脳は、とても効率よく学習しています。
指先を動かす遊びや、想像力を広げる活動をしている間に、思考力や理解する力が伸びています。親から見ると「遊んでいるだけ」に見える時間も、実は大切な集中トレーニングになっています。
この状態に入っている時に、話しかけられたり、急に中断させられたりすると、集中力が途切れやすくなります。
だからこそ、子どもの表情や姿勢から「今、夢中だな」と気づき、その時間をなるべく保ってあげるサポートが重要です。
終わった後には「すごく集中してたね」と声をかけると、自分の中にある集中する感覚を意識できるようになります。
これが次回の集中スイッチを作ります。
他の子と比べず、自分のペースを大切にできる子は、集中力が途切れにくい傾向があります。
周りを気にしすぎると
「あの子の方が早い…」
「できない自分が恥ずかしい…」
という気持ちが先に立ち、集中力が働かなくなってしまいます。
逆に、自分で決めた目標に向かって取り組む経験が積み重なると、自信が生まれ、さらに意欲が湧きます。「自分で決めた」という感覚は、強いエネルギーになります。
家庭では「今日はここまでできたらOK」といった、その子だけの小さな基準を示すと、自然と落ち着いて取り組めます。達成できたらしっかり認めることで、学びに向かう姿勢が育ちます。
一歩ずつ階段を上るように進むことができる子は、後からぐっと伸びる力を秘めています。
急がせず、その子のペースを尊重することです。それが子供の集中力と成長の両方を支える、大切な関わり方です。
子どもの集中力は、毎日の小さな工夫で伸びます。すべてを一度に変える必要はありません。続けやすい仕組みを少しずつ足します。
ここでは、今日から始められる具体策を紹介します。すぐに始められる小さなステップの習慣化で、集中のスイッチが自然に入るようになりますよ。

まずは学習する場所を決めます。机の上は「鉛筆二本・消しゴム・時計」の三点だけにします。
足が床につく椅子にし、背すじが楽に伸びる高さに整えます。照明は手元をやさしく照らします。視界におもちゃやデジタルデバイスが入らない工夫も効果的です。
勉強を始める合図はいつも同じ手順にします。
机を拭く
砂時計を置く
今日の一言目標を声に出す
などルーティンを決めておきます。
終わる時も同じです。
ノートを閉じる
使った物を戻す
学んだ痕跡が分かる一枚を壁に張る
といった手順を約束で決めます。
毎回同じ流れにすることで、お子さんの集中モードのスイッチが入り、学習の習慣化がしやすくなります。
区切りは、子どもの集中力を守る“リズム”のような存在です。
長く頑張らせるよりも、短い単位で取り組みと休憩を交互に入れる方が、集中の質が安定します。
まずは砂時計やキッチンタイマーを使い、10分以内の一単位をつくりましょう。終わったら必ずミニ休憩を入れます。
たとえば次のようなルーティーンを取り入れましょう。
目を閉じて深呼吸を五回
肩を十秒回す
水を一口飲む
この短い動作で体と気持ちがニュートラルに戻ります。
音楽や映像を使わず、静けさの中で心を落ち着かせるのがポイントです。
再開の合図も毎回同じにします。
「三つ数えたら始めよう」と声に出すだけでも、子どもの頭が“切り替えモード”に入ります。
一区切りを一セットとして、ノートの端に印を付けるのもおすすめです。
印が並ぶと「ここまでできた」という達成感が目に見えてわかり、次の集中を自然と引き出します。
こうしたリズムあるフォローが、持続的な集中力を育てていきます。

子どもの集中力は、親の見守りによって深まります。
ひとりで頑張らせすぎず、最初の一問は横に座っていっしょに取り組んでみましょう。
読みづらい部分があれば親が音読し、手が止まった時には「どこまでわかったかな?」と穏やかに問いかけます。
責めず、導くようにサポートすることで、安心して問題に向き合い続けることができます。
たとえば、
できたら記録シールを貼る
途中であきらめず戻れたらスタンプを押す
そんな小さな仕掛けが「頑張った証」になります。
週の終わりには親子で「できた貯金」を数えてみましょう。増えていく記録が、努力の可視化となって自信を育てます。
子どもは他人との比較よりも、昨日の自分との比較で伸びます。
親が「前より集中できたね」と言葉にするだけで、内側のやる気が静かに強くなります。
こうした成功体験の積み重ねこそが、子どもの集中力を育てる最良のトレーニングです。
スマホや動画は情報が速すぎて、子どもの脳が受け止めきれず、集中のリズムを乱してしまうことがあります。
その一方で絵本や新聞は、ページをめくりながら自分のペースで理解できる“ゆっくりとした刺激”を与えてくれます。
読む・聞く・考えるという過程を経ることで、言葉と想像が結びつき、集中が深まるのです。
たとえば次のような習慣を取り入れてみましょう。
見出しを一緒に音読して内容を一文で言い換える
挿絵の中からお気に入りの部分を探す
天気欄の数字や広告の値段を算数の話題にする
新聞の切り抜きをスクラップして一言コメントを添える
これらはすべて、語彙・理解・思考を刺激する家庭教材になります。
親の声で届く言葉は、安心感を持ちやすく、学びを深めます。
静かにページをめくる時間によって、子どもの集中力はじっくり養われます。
その積み重ねが、考える力と集中力のどちらも伸ばしていきます。
子どもの集中力は、生まれつきの性格だけでなく、日々の「刺激」と「達成感」の積み重ねで育ちます。
その点で、そろばんはまさに集中力を育てるトレーニングにぴったりの学びです。
指を動かし、数をイメージしながら解く時間は、思考と感情をひとつに結びつけます。短い時間でも深く集中でき、学習の持続力を高める土台を作ります。
さらに、最近はオンラインそろばんという新しい学び方が登場し、家庭での環境づくりと組み合わせることで、集中の質をより高められるようになりました。
ここでは、そろばんが集中力に効果的な理由と、家庭で無理なく続けられるオンライン学習の魅力を紹介します。

そろばんは“手で考える算数”とも言われるほど、頭と指先を同時に使う学びです。
玉を動かしながら数をイメージする作業は、まるで「脳を目覚めさせる体操」です。この動きの中で、記憶力・判断力・理解力が一斉に働くため、集中が長く続くようになります。
問題を解くとき、そろばんでは先の動きを予測しながら指を動かします。
その瞬間、子どもの意識は“今この一手”に集中します。答えが出るごとに「できた!」という感覚が積み重なり、やる気と自信が育っていきます。
これは単なる計算練習ではなく、心の持久力を育てる集中トレーニングです。
さらに、研究でもそろばん学習を続ける子どもは、注意力の切り替えや作業記憶が強い傾向にあると報告されています。こうした「集中力と学習効果の関係」については、文部科学省の教育研究データでも詳しく紹介されています。
これは、集中力が長く続く子に共通する脳の働きと同じです。
つまり、そろばんは数を扱う力だけでなく、「集中する力そのもの」を伸ばす効果があるといえます。
詳しくは『集中力を鍛えるならそろばん?選ばれる理由5選と最新研究結果』で、そろばんが集中力を高める理由と最新の研究データを詳しく紹介しています。
数字を扱う力と集中力がどのように結びついているのか、その“科学的な裏づけ”がお分かりいただける内容です。
「家ではなかなか集中できない」という声はよく聞かれます。ですが、オンラインそろばんならその悩みを解消できます。
その理由は、家庭で整えた環境の中で、安心して学べることにあります。慣れた机や静かな空間は、心理的な緊張をやわらげ、集中を保ちやすい土台を作ります。
オンラインそろばんの授業では、画面越しでも講師が一人ひとりの進み具合を見守り、的確に声をかけます。親が常に付き添わなくても、適度な距離感で安心感が生まれ、集中のリズムが保たれます。
さらに、家庭では「始める→取り組む→褒める」のルーティンを作ることで、自然と学習習慣が定着します。
また、オンライン授業は移動がなく時間の区切りが明確なので、集中と休憩の切り替えもスムーズです。
短時間のレッスンでも、そろばんを使うことで脳がすぐに活性化し、“集中スイッチ”が入りやすくなります。
家庭での学びを通して集中力を育てたい方には、オンラインそろばんが理想的です。
『集中力を鍛えるならそろばん?選ばれる理由5選と最新研究結果』では、「ネットdeそろばん」がなぜ集中力を鍛えやすいのか、独自の授業スタイルもご紹介しています。
お子さんの学習状況に応じた、無料体験レッスンもご好評いただいています。お気軽にお問合せ・お申込みください。
子どもの集中力は、安心できる環境と小さな成功体験の積み重ねから育ちます。
そろばんは、数を使いながら思考力と集中力を同時に磨ける学びであり、短時間でも深い集中を生み出します。特にオンラインそろばんなら、自宅の落ち着いた環境でリラックスしながら取り組めるため、家庭での学習習慣づくりにも最適です。
ネットdeそろばんでは、経験豊富な講師が一人ひとりに寄り添い、画面越しでも“できた!”の喜びを実感できるよう丁寧にサポートします。家庭の温かさと教室の集中感が両立した学びで、子どものやる気と自信がぐんぐん育ちます。
まずは【無料体験】で、お子さまの集中力が伸びる瞬間を体感してください。そろばんを通して、“集中できる子”から“夢中になれる子”にも育っていきます。
お子様の成長を後押しする新しい学びの第一歩を、今ここから始めてみませんか?
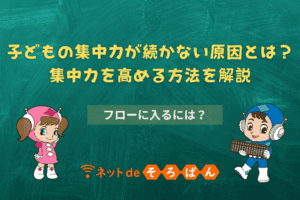
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます