\スグに読める/
\30秒で申込完了/



「最近、子どもが落ち着かない」
「自信が持てていない気がする」
「ついデジタルに頼りがちで心が追いついていない」
そんな不安を抱くご家庭が増えています。便利な時代だからこそ、子どもの心は繊細に揺れやすく、大切な“自分を整える時間”が失われつつあります。
そんな今、多くの親御さんが注目しているのが“アナログ体験”です。
そろばんが集中力やイメージ力を育てるように、水墨画や書道もまた、心の静けさを取り戻し、本来の力を引き出してくれ
る学びです。
今回お話を伺ったのは、女流墨絵アーティストの蓮水(れんすい)さん。書道と水墨画を通して子どもの心の成長を支え、「自分らしさ」を大切にする教育を広げています。
墨をすり、筆を走らせる。そのたびに子どもの心はスッと整い、自己肯定感が育っていきます。この記事では、蓮水先生が語る“和文化教育の本当の力”をわかりやすく紐解いていきます。

「なぜ今、水墨画なのか?」
蓮水先生が初めて書の世界に触れたのは、小学校1年生の頃でした。友達に誘われ、何気なく近所の習字教室へ通い始めたといいます。
それは、ごく普通の習い事のスタートでしたが、彼女にとっては想像以上に大きな意味を持つ時間でした。

筆を持つと自然と心が落ち着くんです。小さかったのに、それがなぜか自分にしっくりきたのを覚えています。
当時の蓮水先生にとって、習字は“文字を上手に書くための練習”ではなく、静かに自分と向き合える特別な時間でした。筆先の動き、墨の香り、半紙が吸い込むインクの感覚、そのすべてが、幼い心を穏やかに整えてくれたのです。
高校生になり、初めて自分の手ですずりで墨をすって字を書くという本格的な書道を体験したとき、彼女はさらに深い世界に惹き込まれます。

墨をする音や香り、濃淡の変化を見ているだけで、すごく心が静かになるんです。あの瞬間、“もっと深く知りたい”と強く思いました。
それが、蓮水先生にとって、墨という素材そのものが持つ魅力に気づいた瞬間でした。
そして大学時代、運命的に水墨画に出会います。白と黒だけで世界を描くという一見シンプルな表現の中に、驚くほど複雑で深い精神性が宿っていたのです。

色がないからこそ、自分の心の動きが全部線に出るんです。迷いも勢いも、静けさも全部。その時の自分が正直に現れるんですよね。
水墨画は“技術を学ぶ”だけの世界ではありません。その一筆が、自分の状態をそのまま映し出す鏡になります。
迷えば線は揺れ、集中するとスッと伸びる。緊張すれば筆が固くなり、心が開けば柔らかい線が生まれる。
AIが文章も絵も作り出せる時代になった今、蓮水先生は「だからこそ水墨画の価値が逆に高まっている」と感じています。

AIには“心の揺らぎ”が描けません。でも水墨画は、その揺らぎこそが作品になるんです。
と語るように、墨の線が持つ“人間らしさ”はどれだけ技術が進化しても再現できないものです。
「なぜ今、水墨画なのか?」この問いの答えは、蓮水先生がたどってきた原点の中にすでにありました。それは “心が現れる線を描くこと” そのものが、今の時代にこそ必要とされているからなのです。
書道の師範まで取得した蓮水先生ですが、一般的な書道教室に対して強い違和感を抱いていたと語ります。それは、「お手本にどれだけ近づけるかが評価になる」指導スタイルに対する疑問でした。

子どもって、本来は筆を動かすだけでも個性が出るんです。でも、お手本通りを書くことだけが正解になると、その魅力が見えなくなってしまうんですよね。
確かに、美しい字を書くための方法としては型にはめることも必要です。
しかし、子どもの線の伸びや筆の勢い、余白の取り方といった“その子ならではの表現”は、型にはめられることでかえって失われてしまう場合があります。
特に、自己肯定感が揺らぎやすい今の子どもたちにとって、「正解は一つ」という指導は窮屈に感じることもあるでしょう。
そこで蓮水先生が選んだのは、「書道 × 水墨画」という全く新しい教育スタイルでした。
書道で培われる集中力や筆使いを土台にしながら、水墨画では自由に表現させるという方法です。

書道で心を整えて、水墨画で心を開放する。両方があることで、子どもが自分らしさを取り戻していくんです。この二つは実は非常に相性の良い組み合わせです。
この指導法は、ネットdeそろばんが掲げる“非認知能力の育成”にも重なります。技術や点数ではなく、内面の成長や自己肯定感を育む教育。
蓮水先生の取り組みはまさにその実践であり、子どもたちにとって理想的な環境といえます。


水墨画は、心の揺れや素直さがすぐに線に出るんです。子どもだと特に、気持ちがそのまま筆にのるので見ていて面白いですよ。
水墨画の面白さは、描いた線にその人の“心の状態”がそのまま映し出されることです。
筆を置く瞬間の迷い、呼吸が整ったときに生まれる伸びやかな線、少し緊張して力が入りすぎた線。すべてが、その瞬間の感情とつながっています。

線を見て“これ、私の気持ちだな”と気づく子も多いんですよ。そういう瞬間を見ると、水墨画って本当に心の教育だなと感じます。
水墨画には、お手本通りに描くという概念がありません。正解も不正解もなく、線の太さや濃淡、構図も、そのときの気持ちのままに描いていい世界です。
だからこそ、子どもたちは肩の力を抜き、ありのままの“自分らしい線”を表現できます。評価されるためではなく、比べられるためでもなく、自分の感情を純粋に表せる安心感。これが、今の子どもたちが特に求めている環境なのかもしれません。
作品として「うまくできた/できなかった」で判断されないことは、自己肯定感の育成に大きく作用します。子どもは「これでいいんだ」「これが自分の線なんだ」と、自分の表現そのものを肯定できるようになります。
そろばんが“できた”という成功体験を積み重ねて自信を育てるのに対し、水墨画は“ありのままの自分でも大丈夫”という存在の自信を育てる学びです。
両方をバランスよく取り入れることで、子どもはより深い自己肯定感を手にし、心にしなやかな強さを持てるようになります。
最近では、美しく整った文字を書くことに価値が置かれ、SNSでも“美文字”が注目されています。しかし蓮水先生は、「字の美しさだけが書道の本質ではありません」と語ります。
習字と書道は似ているようで実は目的がまったく違い、習字は“正しい形に整える技術”を学ぶものである一方、書道は“心と向き合い、その状態を筆に宿す文化”だといいます。

書道って、ただ上手に書くための練習ではなくて、呼吸や心の静けさまで作品に出るんです。そこが魅力なんですよね。
この違いは、日本文化に深く根づく“道(どう)”の精神にも表れています。
茶道・華道・武道など、名前に“道”がつくものにはすべて、技術と精神性が両輪で存在しています。書道も同じで、筆の運び方や線の強弱には、その人がどんな気持ちで臨んでいるかが明確に反映されます。
心が落ち着いていれば線はまっすぐ伸び、焦りがあれば迷いが線の揺れとして現れる。書道は、技術以上に“内面の状態”を映す鏡でもあるのです。
最近の環境では、デジタル機器や情報の多さによって気持ちが散りやすく、集中が続きにくい環境にあります。そんな中で、書道がもたらすゆっくりとした呼吸、墨の香り、筆を運ぶ時間は、子どもにとって心を整える貴重なひとときになります。

筆を運んでいると、自然と気持ちが静かになる子が多いんです。集中しようと頑張るのではなく、自然と整っていく感覚ですね。
そろばんの学習でも“無心で集中に入る瞬間”があるように、書道もまた心を静かに整える力を持っています。習字では学べない精神的な深さ、それこそが、書道の本質的な価値だといえます。

書道や水墨画に取り組む中で、蓮水先生が特に大切にしているのが「言霊(ことだま)」という考え方です。
言霊とは、日本語の一音一音に“意味や力が宿る”という日本文化の根本にある思想です。「日本語って、母音のひとつひとつに意味があるんです。“あ”は始まりの音、“う”は生み出す力……そう考えると、言葉を大切にしたくなりますよね」と蓮水先生は語ります。
最近では、略語や外来語が増え、言葉の使い方がどんどん軽くなっています。もちろん便利ではありますが、その分、言葉に込められる感情や丁寧さ、相手を思う気持ちが薄れやすい環境になっています。
子どもが幼い頃から日本語の“心に触れる感覚”を育てることは大切です。それは、自己表現やコミュニケーションの基礎にもつながるからです。
言霊を学ぶことは単に知識を増やすのではなく、“心の使い方”を学ぶことでもあります。
例えば、怒って発した言葉は自分の心にも影響し、丁寧な言葉遣いは落ち着きをもたらします。これは心理学的にも正しく、言葉と感情は密接に結びついています。

言葉が乱れると心も乱れるんです。逆に、言葉を丁寧に扱うと、心が自然と整っていきます。
さらに、日本語は他の言語と比べても“音の響きが情緒に直結しやすい”特徴を持っています。発音そのものが感情を表し、声のトーンが相手の気持ちの受け取り方を大きく左右します。
子どもがこのことに気づくと、自分の気持ちや相手の気持ちに敏感になり、思いやりや気遣いが自然と育っていきます。
そろばんが“集中力・数の感覚・右脳の力”を育てるとすれば、言霊や書道は“言葉・心・情緒の力”を育てる存在です。両方が合わさることで、子どもの内面はより豊かに、強く、美しく育っていきます。
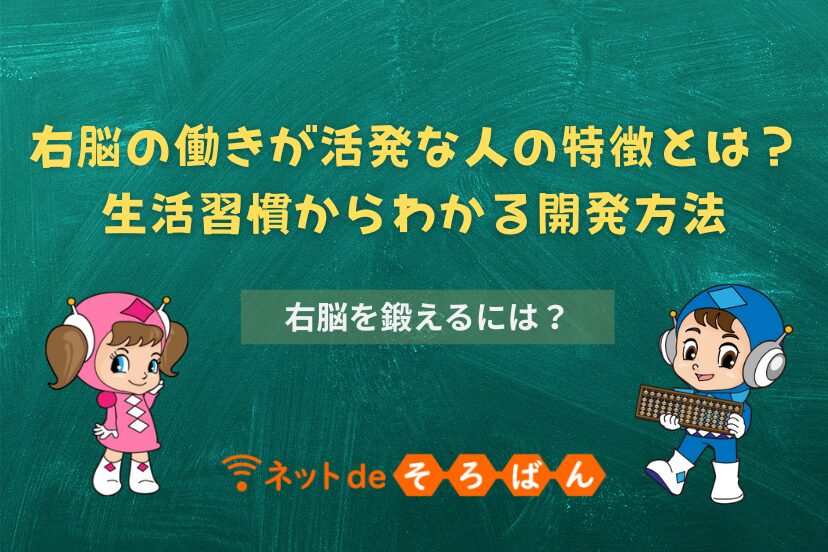
スマホやタブレットが手放せない今の子どもたちは、常に多くの情報にさらされています。
便利な反面、脳は休む暇をなくし、心は刺激に慣れ、落ち着く時間を持つことが難しくなっています。そんな環境において、書道や水墨画が与える“ゆっくりとした時間”は、子どもの心を整える貴重な体験になります。
蓮水先生は、墨をすり始める瞬間の空気が大好きだと話します。

墨を丁寧に磨って、墨の香りが漂ってくると、自然と心が落ち着いて呼吸も深くなるんです。
筆を整え、一筆置くまでの一連の動作には、デジタルでは再現できない“間(ま)”があります。この間こそが、心を整える鍵です。
筆を動かしているとき、子どもは自然と呼吸が整い、姿勢が正しくなり、集中力が高まります。これは“集中しよう”と意識して努力しているわけではなく、書画という行為そのものが本来持つ力によって、自然と心が落ち着いていくのです。

筆を動かしていると、みんなスッと無心になるんです。意識して集中するんじゃなくて、気づいたら集中している。その瞬間がとてもいいんですよね。
墨を磨る行為は、まさにマインドフルネスであり、この無心の時間は心理学で言うフロー状態です。それが、心の安定・情緒の発達に大きく影響します。
デジタル刺激に慣れた子どもほど、この静かな時間を体験することで、自分の内側に意識を向けることができるようになります。そろばんにも同じ効果があり、集中しているときの静けさは共通しています。
書画の時間は、ただの習い事ではなく、子どもが“本来の自分”へ戻るための大切なリセット時間です。AIが進化する時代だからこそ、人間にしか持てない“心の深さ”を育てるこうしたアナログ体験が、より重要になっているのかもしれません。
水墨画の世界には、「上手い」「下手」という評価軸が存在しません。線が曲がっていても、濃すぎても薄すぎても、それが“今の自分のままの線”であり、そこに価値があります。
この自由さこそが、子どもの心に驚くほど良い影響を与えます。

子どもたちの線って、本当に正直なんです。いい意味でごまかせなくて、そのまま心が出るんですよ。
学校やテスト、SNSなど、多くの場面で評価や比較を経験しやすくなっています。
そのため “間違えてはいけない” という意識が強く、絵を描くことにも苦手意識を持つ子が増えているのが現状です。
しかし、水墨画ではそのプレッシャーから解放されます。線を引くたびに、「これでいいんだ」「この線は自分だけのものだ」と、自然と自信を積み重ねることができます。
蓮水先生は、子どもたちが作品を見て喜ぶ瞬間を何度も見てきたといいます。

“これ私の気持ちだ”って自分で気づく子もいるんですよね。あの瞬間、自分自身を受け入れている表情になるんです。
水墨画は、努力して技術を積み重ねる学びとは違い、存在そのものを肯定する学びです。だからこそ、自己肯定感の育ちにくい今の子どもにとって、非常に大きな価値があります。
そろばんが正確さと集中力によって「できた!」という成功体験を積ませてくれるのに対し、水墨画は「そのままでいい」という安心感を与えてくれます。両方を併用することで、子どもは“技術の自信”と“存在の自信”の両方を手にし、心の根っこがしっかり育っていきます。

書道や水墨画の教室を続けるなかで、蓮水先生は「文化は家庭から伝わる」という大切な真理にたどり着いたといいます。

子どもは親が大事にしているものを自然と真似するんです。だから、日本文化の良さに触れる最初のきっかけは、実は家庭にあるんですよね
親の姿勢は子どもの文化観に強い影響を与えます。
日本文化は、単なる“古いもの”ではありません。心の使い方、呼吸、間(ま)の取り方、言葉の丁寧さなど、現代にも通じる豊かな知恵が詰まっています。
書道や水墨画には、まさにその本質が凝縮されています。墨の香り、筆を運ぶ動作、作品と向き合う静かな時間、これらは、家庭で子どもが落ち着きを取り戻すためのきっかけにもなります。
蓮水先生は、家庭でも簡単に取り入れられる方法を教えてくれました。

筆などのお道具を丁寧に扱ったり、言葉遣いに気を付けるなど、日々の小さな心掛け、習慣が子供の心を整えます。
こうした小さな積み重ねが、子どもの“文化的感性”や“情緒の安定”につながっていきます。
また、和文化とそろばんには驚くほど共通点があります。どちらも静かな集中、所作の美しさ、心の落ち着きを重んじる学びです。
そろばんで右脳と集中力を育て、書画で情緒と心の安定を育むことで、子どもはバランスよく成長することができます。AI時代を生きる子どもたちにとって、この“アナログの心育て”は確実に価値を増していくでしょう。
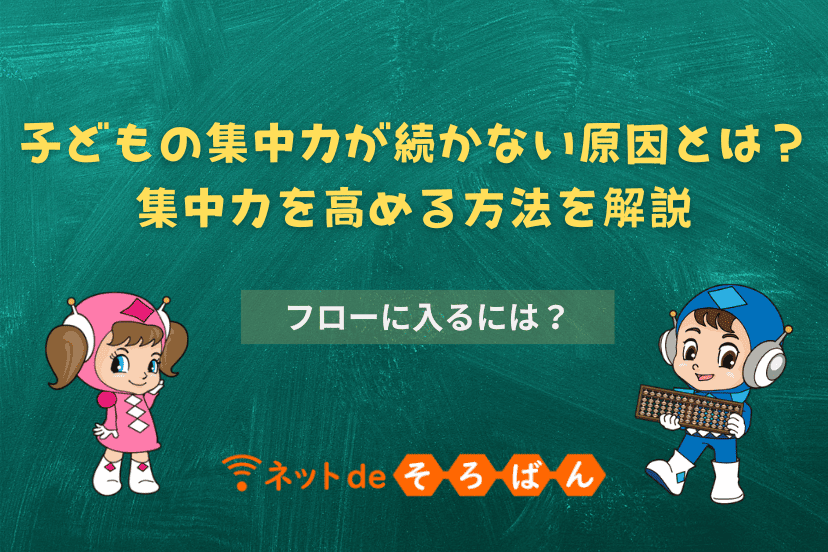
文化は学校だけではなく、家庭でこそ育まれます。親がほんの少しだけ日本文化を大切にする姿を見せるだけで、子どもは自然とその価値を感じ取っていくのです。
蓮水先生は、水墨画を通して子どもたちが育てた“感性”や“心の動き”を、もっと多くの人に知ってほしいと考えています。

日本人の叡智である水墨画を次世代に繋げ、子供の素晴らしい感性で描かれた作品をもっと外の世界伝えられたらいいなと思っています。
子どもが描く水墨画には、技術を超えた純粋なエネルギーがあります。
そして、最近ではアートと教育を組み合わせる試みが世界的に注目されています。
自分を表現する力は、将来につながる重要な非認知能力のひとつです。そこに、そろばんで培われる集中力・数の感覚・判断力が合わされば、子どもたちはより高いレベルで自己表現ができるようになります。右脳のイメージ力と左脳の論理力がバランスよく鍛えられ、創造性の土台が整うためです。
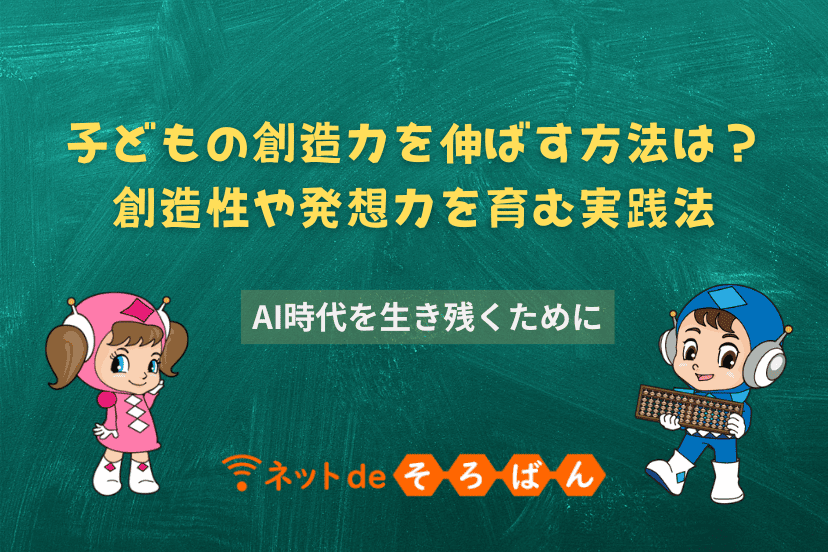
蓮水先生は、水墨画とそろばんを組み合わせることで生まれる“未来の教育の可能性”に強い期待を寄せています。

感性って、伸ばしてあげたら本当にどんどん広がるんです。そこにそろばんの集中力が加わると、自分の表現に芯が通ってくるんですよね。
また、デジタルの進化によって、子どもたちの作品を発信する方法は無限に広がっています。オンライン展示会、海外のアートコミュニティ、国際的な子どもアートコンテストなど、発表の場を選ばず世界へ届けることができます。
これは、子どもにとって大きな成功体験になり、自信にも直結します。
水墨画は“心を映す線”。
そろばんは“集中を生むリズム”。
このふたつが合わさることで、子どもたちの可能性はさらに豊かに広がり、世界に向けた新しい表現の形が生まれるはずです。
ここまで読んでくださって、きっとお子さまの姿が少し浮かんできたのではないでしょうか。子どもの感性は、環境と出会いで大きく変わります。
子どもの感性は、環境と出会いで大きく変わります。もし今、「もっと心が伸びる学びを体験させたい」と感じているなら、水墨画はとてもおすすめです。
一筆ごとに心が整い、自分を認める土台が育つ。その変化を、あなたのお子さまでも感じてみませんか?

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます